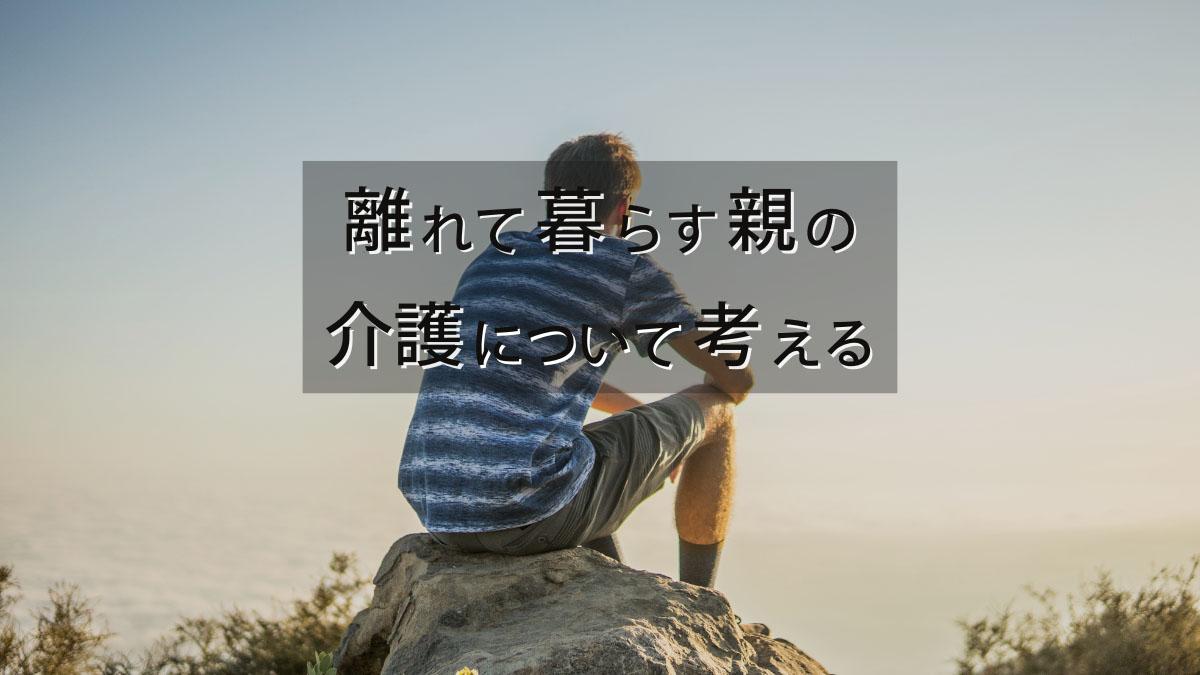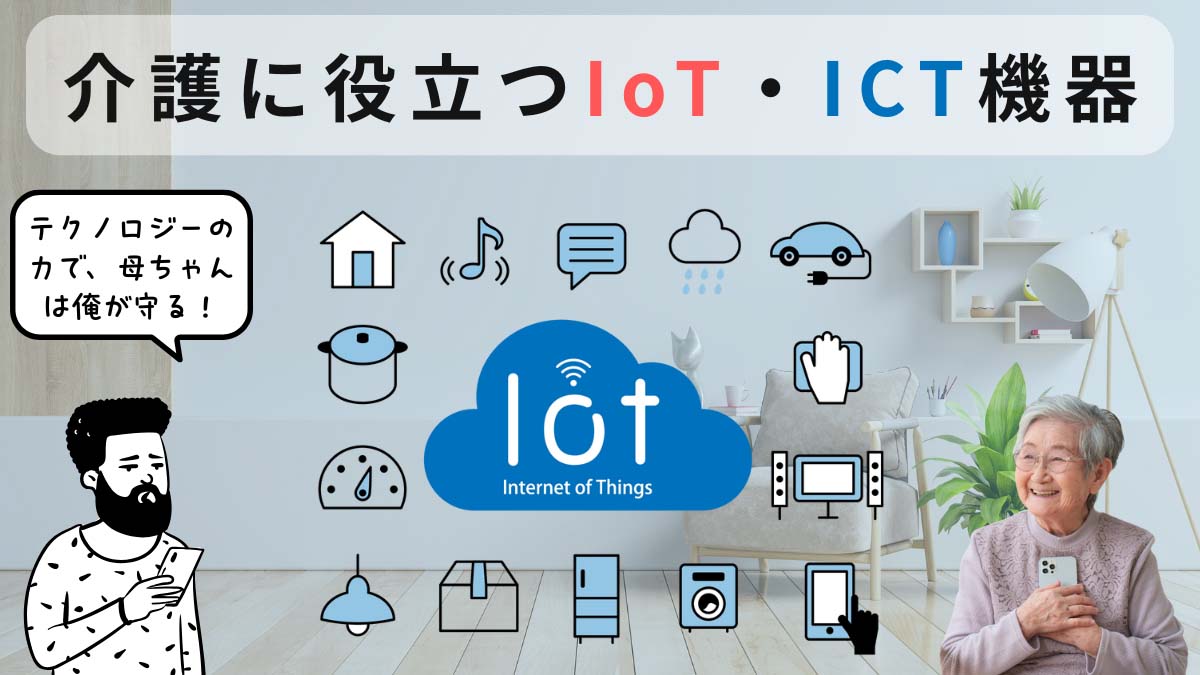
高齢化が進む現代において、在宅介護は多くの人にとって身近なものとなりました。そうした中、介護者の負担を軽減し、介護を受ける方が安心して暮らせるよう、見守りIoTやICTを活用した介護支援システムが注目されています。
Memo
「IoT」とは、モノがインターネットにつながる仕組みのこと。例えば、センサーやカメラなどを使って、離れた場所からでも家族の様子をスマホなどで見守れるシステムです。
「ICT」とは、情報通信技術のこと。パソコンやインターネット、スマホなどを使って、情報のやり取りをスムーズにする技術全般を指します。介護の分野では、介護記録を共有したり、遠隔でコミュニケーションをとったりするのに役立ちます。
介護の負担を軽くしてくれる見守りIoT・ICT機器ですが、種類がたくさんあって「どれを選んだらいいの?」「どうやって使えば介護が楽になるの?」といった疑問から、まだ毎日の生活に広く取り入れられているとは言えません。
そこでこの記事では、介護者の目線に立ち、具体的な製品の選び方から導入のメリット・デメリット、実践的な見守りIoT・ICTの活用術をご紹介します。
なぜ今、見守りIoT・ICTが必要なの?在宅介護のニーズがどんどん高まっている背景
在宅介護では、介護者はさまざまな課題に直面します。例えば、24時間見守ることのプレッシャー、夜間の徘徊や転倒への心配、そして薬の管理の難しさなどが挙げられます。これらの負担に加え、介護者の孤立感も深刻な問題です。
こんな状況の中で、見守りIoT・ICTは、介護者の「見守り」や「安否確認」の負担をぐっと減らし、精神的な安心感をもたらしてくれます。それだけでなく、介護される側が自分でできることを増やし、より質の高い生活を送れるように助けてくれる可能性もあります。
見守りIoT・ICTの種類と選び方

今、市場には様々な機能を持った見守りIoT・ICT機器がたくさん出ています。それぞれの特徴をよく理解して、介護される側の状態や、介護者の「こうしたい」というニーズに合ったものを選ぶのが大切です。
スマートセンサー・非接触型センサー
どんなもの?
ベッドの下や部屋の中に設置することで、眠っている時間、ベッドから起き上がったタイミング、どれくらい動いているかなどを感知してくれるセンサーです。カメラを置くことに抵抗がある方や、プライバシーを大切にしたい場合にとても役立ちます。
主な機能
- 離床センサー:ベッドから落ちたり、立ち上がったりしたときに知らせてくれます。
- 睡眠センサー:眠りの深さや、寝返りの回数などを記録して、睡眠の質が目で見てわかるようにしてくれます。
- 生活リズムセンサー:ある程度の時間、全く動きがなかったときに異変を知らせたり、いつもの生活リズムと違う動きを検知してくれます。
選ぶときのポイント
- どこまで正確に検知できるか:間違いの通知が少ないか、小さな動きもきちんと拾ってくれるか。
- 取り付けは簡単?:工事がいらず、すぐに設置できるか。
- どうやってお知らせしてくれる?:スマホアプリやメール、緊急呼び出しボタンとの連携など、介護する方が一番使いやすい通知方法かを確認しましょう。
導入事例1
Aさん (80代・要介護1)は夜中にトイレへ行く際の転倒が心配でした。そこで、ベッドのそばに非接触型センサーを設置。Aさんがベッドを離れると、同居するご家族のスマートフォンにすぐに通知が届き、すぐに駆けつけられるようになりました。
さらに、睡眠センサーの記録からAさんの睡眠の質が低下していることも判明。これが、生活リズムを見直すきっかけにもなっています。
見守りカメラ
「離れていても、介護が必要な家族の様子を確認したい」そんな思いに応えるのが、見守りカメラです。
どんなもの?
自宅に設置して、スマートフォンやパソコンからリアルタイムで部屋の様子を見られるカメラです。介護される方の表情や動きを直接見られるので、今どんな状況なのかをしっかり把握できます。
主な機能
- ライブ映像・録画:今の映像を見たり、後から録画を見返したりできます。
- 音声通話:カメラを通して、お互いに話すことができます。
- 動くものや音を検知:変な動きや音を察知すると、お知らせしてくれます。
- 暗い場所でも見える機能:夜間でもはっきりと映像を確認できます。
選ぶときのポイント
- 映像のきれいさ・見える範囲:クリアな映像で、広い範囲が見えるか。
- プライバシーへの配慮:使わないときは電源をオフにしたり、必要な時だけオンにできる設定があるか。
- 使いやすさ:アプリの操作が簡単で、誰でも迷わず使えるか。
導入事例2
Bさん (80代・認知症)は軽度の認知症があり、目を離すとどこかへ行ってしまう心配がありました。リビングに見守りカメラを設置したところ、ご家族は外出先からでもスマートフォンのアプリでBさんの様子をリアルタイムで確認できるようになりました。動体検知機能でBさんが部屋を離れようとすると通知が来るため、すぐに電話で声をかけたり、必要に応じて近隣の親戚に連絡したりと、迅速な対応が可能になり、介護者の心理的な負担も軽減されました。
服薬支援ロボット
主な機能
薬の飲み忘れや、間違って飲んでしまうのを防ぐ機器です。設定した時間になると音や光で『お薬の時間ですよ』と知らせる機器もあり、中には服薬したかどうかを記録し、それを介護者に通知する機能を備えたものもあります。さらに、水分補給を促す機能がついたタイプもあります。
どんなもの?
- 服薬アラーム:設定した時間になると、音や光で薬を飲むように促します。
- 自動で薬を出す:決まった時間になると、自動で薬が出てきます。
- 薬を飲んだか管理:薬を飲んだかどうかの記録を残し、介護者に通知してくれます。
選ぶときのポイント
- 操作のしやすさ:高齢の方でも簡単に使えるか。
- 対応できる薬の種類:何種類もの薬や、量が多い場合にも対応できるか。
- お知らせ機能:介護者へのお知らせ方法が、自分に合っているか。
- 購入・レンタル:購入だけでなく、無料や有償でレンタルできる場合もあります。
Memo
介護保険を利用している場合は、かかりつけ薬局やケアマネジャーに相談しましょう。在宅医療サービスの利用有無が、無料レンタルの可否に関わる場合があります。
導入事例3
Cさん(80代・認知症、一人暮らし)は軽度の認知症があり、薬の飲み忘れが心配されていました。服薬支援デバイスを導入したところ、設定した時間になると自動で薬が出てくるようになり、飲み忘れが激減しました。また、ご家族のスマートフォンに服薬状況が通知されるため、離れて暮らしていても安心感を得られるようになりました。
コミュニケーションロボット・AIスピーカー
どんなもの?
おしゃべりすることで、高齢者の方の寂しさを和らげたり、頭の体操を促してくれるロボットやAIスピーカーです。中には、安否確認や緊急連絡の機能を持っているものもあります。
主な機能
- 日常会話:高齢者の方の話し相手になってくれます。
- お知らせ機能:薬を飲む時間や外出する時間を教えてくれます。
- 脳トレゲーム:記憶力や考える力を刺激するゲームで遊べます。
- 緊急連絡機能:高齢者の方が「具合が悪い」と訴えたときに、登録しておいた連絡先に知らせてくれます。
選ぶときのポイント
- 自然な会話ができるか:高齢者の方が抵抗なくお話できるか。
- 機能が充実しているか:おしゃべり以外の機能も、自分たちのニーズに合っているか。
- プライバシーは大丈夫?:話した内容などが適切に扱われるか。
導入事例4
一人暮らしで寂しさを感じていたDさん(80代、要支援2)。孫からプレゼントされたコミュニケーションロボットを導入すると、毎日楽しそうに会話するようになりました。このロボットは家族とも会話ができるため、離れて暮らす孫もDさんの様子を把握でき、安心して見守れるようになりました。
その他の見守りIoT・ICT:スマートロック・見守りタグなど
ここまでご紹介した以外にも、日々の暮らしを支え、介護の負担を軽減してくれる便利なIoT・ICT機器があります。
- スマートロック:ドアの鍵がかかっているかをスマホで確認したり、開け閉めを操作できるので、鍵の閉め忘れを防いだり、訪問介護サービスの方が来る時に便利です。
- 見守りタグ・GPS:外出先で迷ってしまうなど、自力で帰宅が難しくなる場面を想定し、現在地を確認できる機器があります。小型で持ち運びやすく、介護される方の安心と安全をサポートします。
- 遠隔操作エアコン:スマートフォンなどからエアコンのオン/オフや温度設定ができるため、離れて暮らす家族や外出中の介護者でも、自宅にいる子高齢者が快適に過ごせるように室温を調整できます。
見守りIoT・ICTの導入効果と注意点

見守りを支えるIoT・ICT機器の導入は、介護に役立つさまざまなメリットが期待されます。ただし、導入に際しては注意が必要な点もあります。
導入のメリット
見守りIoT・ICT機器を導入することで、介護を受ける方だけでなく、介護をする側にとっても多くの良い変化が生まれます。
- 介護負担の軽減:24時間見守る必要がなくなり、身体的・精神的な負担を大幅に減らします。特に夜間の見守り不安が解消され、介護者の睡眠の質向上につながります。
- 安心感の向上:離れていても介護される方の状況がわかるため、不安が減り、介護する側に心のゆとりが生まれます。介護される方も、「見守られている」という安心感を得られます。
- もしもの時の早期発見:転倒や急な体調不良といった異変に早く気づき、すぐに対応できる可能性が高まります。
- プライバシーの尊重(一部):カメラに抵抗がある場合でも、非接触型のセンサーならプライバシーを気にしすぎることなく見守りができます。
- 自立の促進:必要以上に手出しせず、介護される側の能力を大切にすることで、自立した生活を応援できます。
- 客観的な状況把握:睡眠時間や活動量、服薬状況などがデータとして記録されるため、医師やケアマネジャーとの情報共有にも役立ちます。
導入時の留意点
見守りIoT・ICT機器の導入は多くのメリットがある一方で、いくつか注意しておくべき点や、潜在的なデメリットも存在します。導入を検討する際は、これらの点をしっかりと理解し、適切な対策を講じることが重要です。
- 「監視されている」と感じる可能性:特にカメラを使用する場合、介護される方が「見張られている」と感じ、ストレスや不快感を抱くことがあります。導入前に本人と十分に話し合い、同意を得ることが極めて重要です。
- 誤報や過剰な通知:センサーの感度設定によっては、誤った情報が届いたり、必要以上に頻繁な通知が発生することがあります。
- 機器の故障・通信の不具合:電子機器であるため、故障やインターネット接続の不具合が発生する可能性はあります。定期的な点検や、万が一の事態に備えた対策を検討しておく必要があります。
- 費用:機器の購入費用に加え、月額の利用料が発生する場合があります。自治体からの補助金制度などを活用できるか、事前に確認しておきましょう。
- 設定や操作の複雑さ:高齢の介護者やIT機器の操作に不慣れな方にとっては、初期設定や日々の操作が難しく感じられることがあります。
- テクノロジーへの過信:これらの機器はあくまで介護のサポートツールです。完全に任せきりにしてしまうと、かえって緊急時の対応が遅れるリスクも考えられます。
- バッテリー切れや電源オフ:電池駆動のデバイスでは充電忘れ、または意図せず電源が切れてしまうことで、見守り機能が停止する可能性があります。
導入を成功させるための秘訣

見守りIoT・ICT機器の導入は、単にデバイスを設置するだけでは終わりません。事前の準備と、導入後の継続的な工夫が、その効果を最大限に引き出す鍵となります。
事前準備:介護される側の理解とお互いの合意
何よりも大切なのは、介護される方本人の気持ちを尊重し、時間をかけてじっくり話し合うことです。導入理由を、優しく丁寧に伝えて、納得してもらうことが不可欠です。一方的に導入してしまうと、「見張られている」と感じてしまい、かえって関係が悪くなる原因にもなりかねません。
- 何のために使うのかを考える:「転ばないようにするため」「夜中にちゃんと寝ているか知るため」「薬の飲み忘れを防ぐため」など、具体的な目的を明確にすることで、一番合った機器を選べます。
- 専門家へ相談してみる:ケアマネジャーや福祉用具貸与・購入ができる事業所、地域包括支援センターに相談して、介護される方の状態や、どんなサポートが必要か、アドバイスをもらいましょう。
- いろんな製品を調べて比べてみる:複数の製品の機能、値段、サポート体制などを比較検討し、実際に使った人の感想やレビューも参考にしましょう。もし可能なら、実際にデモ機を試してみるのもおすすめです。
- 費用と補助金制度のチェック:介護保険が使える場合や、自治体や企業からの補助金制度がある場合があります。事前に調べて、使えるものは積極的に活用しましょう。
導入後の使い方:無理なく、長く続けられる工夫を
見守りIoT・ICT機器は、導入して終わりではありません。日常生活に定着させ、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかの工夫が必要です。
- 少しずつ始めてみる:いきなり全ての機能を使い始めるのではなく、まずは本当に必要な機能から始めて、徐々に慣れていくのがおすすめです。
- 操作に慣れる練習:介護者だけでなく、介護される側も簡単な操作ができるように、一緒に練習してみましょう。
- 定期的なチェックと手入れ:機器の充電、インターネットのつながり具合、センサーの汚れなどを定期的に確認して、いつも正常に動いている状態を保ちましょう。
- 頼りすぎないこと:テクノロジーはあくまで手助けしてくれる道具です。完全に任せきりにしてしまうのではなく、これまで通り、こまめな声かけや訪問、必要に応じて体を支えてあげたりすることも忘れずに。
- 家族みんなで情報を共有:もし複数の人が介護に関わっているなら、見守り状況や連絡事項を共有するルールを決めておくと、みんなでスムーズに連携できます。
終わりに:テクノロジーを味方につけて、もっとゆとりのある介護へ
見守りIoT・ICTは、介護者の負担を軽くし、介護される人が安全で安心して生活できるように支えてくれる、心強い味方です。 しかし、ただ機器を導入すれば全てが解決するわけではありません。大切なのは、介護される側と介護者の双方にとって一番良いバランスを見つけ、テクノロジーを賢く活用することです。
この記事でご紹介した情報を参考に、あなたの介護状況にぴったりの見守りIoT・ICTを見つけ、よりゆとりのある介護生活を実現できるよう、ぜひ活用を進めていきましょう。