
介護はさまざまなきっかけで始まり、その責任と日々の負担で疲れ切ってしまうこともあります。そんなとき、周囲からの何気ない一言が、かえって介護者の心を深く傷つけ、追い詰めてしまうことも少なくありません。
この記事では、介護で疲れている人が「言われてつらい」と感じるNGワードとその理由、そして介護者の心を本当に支えるための言葉の選び方について解説します。もしあなたの周りに介護を頑張っている方がいたら、ぜひ最後まで読んで、その方の心を癒すためのヒントを見つけてください。
なぜ「言ってはいけない言葉」があるのか?
介護疲れは、肉体的な疲労だけでなく、精神的なストレスや孤独感、将来への不安など、複雑な感情が絡み合って生じます。そんなデリケートな状態にある介護者にとって、不用意な言葉は以下のような影響を与えかねません。
- 誤解や無理解による孤独感の増幅
介護者の苦しみが理解されていないと感じ、孤立感を深めてしまいます。
- 責任感や罪悪感の増大
「自分がもっと頑張らなければ」というプレッシャーや、「自分はダメな介護者だ」という罪悪感を抱かせてしまうことがあります。
- 精神的負担の増加
すでに疲弊している心に、さらに追い打ちをかけることになり、ストレスを悪化させます。
- 相談することへの躊躇
「どうせ理解してもらえない」と感じ、悩みを打ち明けることをためらうようになります。
介護疲れの人に「言ってはいけない」NGワード集

具体的なNGワードと、なぜその言葉が問題なのかを見ていきましょう。
NGワード1:「みんなやっていることだから」「介護は当たり前」
【なぜNGなのか?】
介護は決して「当たり前」ではありません。それぞれの家庭環境や被介護者の状況は千差万別で、同じ介護は一つとしてありません。この言葉は、介護者の特別な努力や苦労を軽視し、「自分のつらさは甘えなのか」と感じさせてしまいます。
NGワード2:「もっと頑張って」「あなたがしっかりしないと」
【なぜNGなのか?】
介護者はすでに十分頑張っています。これ以上「頑張れ」と言われることは、精神的なプレッシャーとなり、休むことへの罪悪感を生みます。また、「あなたがしっかりしないと」という言葉は、介護者にすべての責任を押し付け、孤立させることにもつながります。
NGワード3:「〇〇さん(他の介護者)はもっと大変なのに」
【なぜNGなのか?】
他者との比較は、介護者の苦しみを相対化し、その人の感情を否定することになります。苦しみに大小はありません。この言葉は、「自分のつらさは大したことない」と思い込ませ、SOSを出しにくくさせてしまいます。
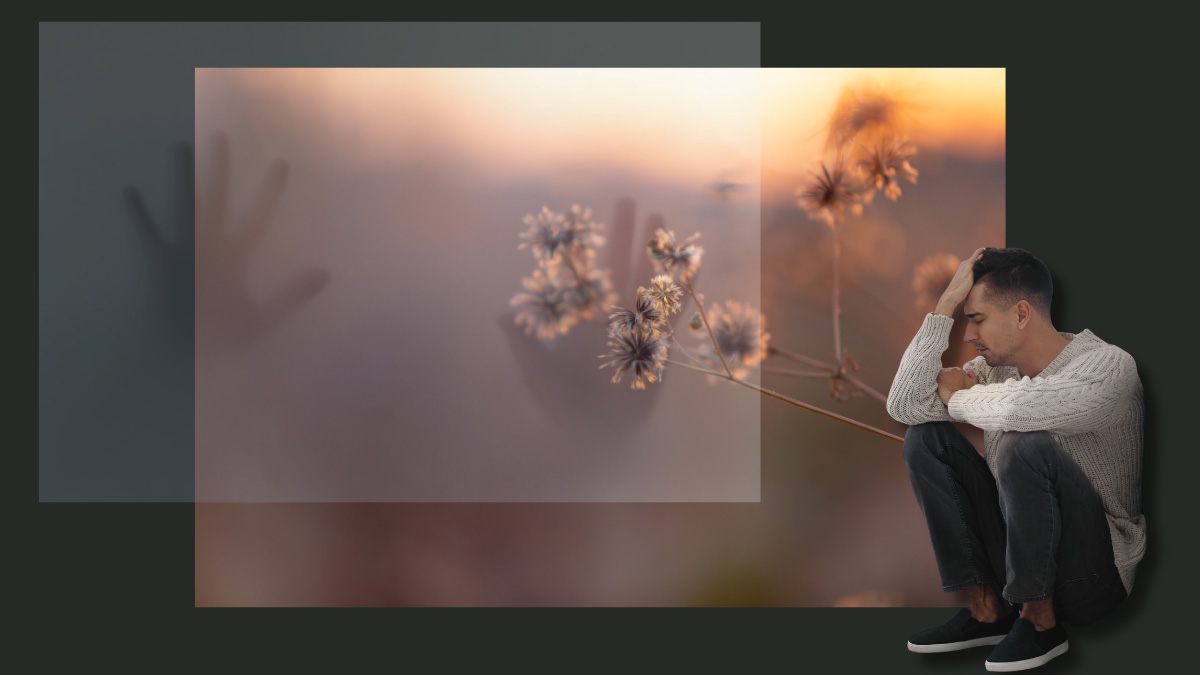
NGワード4:「まだ若いんだから大丈夫でしょ?」「〇〇さんより楽でしょ?」
【なぜNGなのか?】
年齢に関わらず、介護の負担は大きいものです。若いから体力がある、若いから頑張れる、という安易な決めつけは、介護者の疲労や悩みを過小評価することになります。
また、「〇〇さんより楽でしょ?」といった他者との比較は、介護者の苦労や感情を否定し、その人のつらさを軽んじる行為です。 介護の状況は人それぞれ異なり、比べることはできません。精神的な疲弊は、年齢や他者の状況とは関係なく、誰にでも訪れるものです。
NGワード5:「大変なら施設に預ければいいのに」「プロに任せれば?」
【なぜNGなのか?】
施設入所やプロへの依頼は、介護者にとって金銭面や家族の意向など、様々な要因が絡む大きな決断です。安易に「〇〇すればいい」と言うことは、「私たちの苦悩を理解していない」と受け取られ、不信感を与えてしまいます。
プロの力を借りること自体は有効な選択肢ですが、この言葉がNGなのは伝え方とタイミングに問題があるからです。介護者の状況を理解せず、一方的に解決策を押し付ける言い方は、疲弊した心をさらに傷つけかねません。
大切なのは、介護者の気持ちに寄り添い、具体的な状況を理解した上で、「プロの力を借りることも考えてみては」と提案の形で優しく伝えることです。
NGワード6:「〇〇さん(介護される側)もつらいんだから我慢して」
【なぜNGなのか?】
介護される側のつらさも理解できるものの、介護者のつらさを無視して我慢を強いる言葉です。介護者は、介護される人のことを第一に考えているからこそ介護を続けています。この言葉は、介護者の献身を当たり前とみなし、さらに負担をかけることになります。
NGワード7:「何か手伝うことある?」
【なぜNGなのか?】
一見親切に聞こえますが、具体性がなく、介護者からすると何を頼んでいいか分かりません。また、忙しい中で頼み事を考える負担を与えてしまうこともあります。本当に助けたいなら、もっと具体的な提案が必要です。
NGワード8:「介護は親孝行だから」「親を介護するのは子供の義務」
【なぜNGなのか?】
介護は、親への感謝や愛情から行われる場合もありますが、それがすべてではありません。「親孝行」や「義務」といった言葉は、介護者にさらなる精神的なプレッシャーを与え、疲労困憊の状態であっても休むことを許さないような罪悪感を抱かせてしまいます。介護者の自己犠牲の上に成り立つものであってはならず、精神的な負担を増大させる原因となります。
介護者の心を支える「寄り添う言葉」とは?

では、介護で疲れている人には、どのような言葉をかけるのが良いのでしょうか。大切なのは、共感と労い、そして具体的なサポートの意思表示です。
- 「いつも本当に大変だね、よく頑張っているね」
介護者の努力を認め、労う言葉です。シンプルですが、「あなたの頑張りを見ているよ」というメッセージが伝わり、心が安らぎます。
- 「ゆっくり休めている?」
介護者の体調を気遣う言葉です。休むことへの許可を与えるようなニュアンスも含まれ、心の負担を和らげます。
- 「何かあったら、いつでも話を聞くよ」
具体的な解決策はなくても、話を聞く姿勢を見せることで、介護者は孤立感を和らげることができます。無理にアドバイスしようとせず、ただ耳を傾けることが大切です。
- 「私にできることがあったら、遠慮なく言ってね。例えば〇〇(具体的な提案)とか」
「何か手伝うことある?」よりも、具体的に何ができるかを提示することで、介護者は頼みやすくなります。
相手との関係性や、あなたが提供できる時間・スキルに合わせて、できる範囲で相手の重荷にならないことにも配慮しましょう。例えば、「買い物に行くついでに何か買ってこようか?」「数時間だけ代わりに見ているよ」「ご飯作ろうか?」「話を聞くことならできるよ」「ネットで役立つ情報を探してみようか?」など、具体的な提案が有効です。
- 「一人で抱え込まずに、周りを頼っていいんだよ」
介護者は、「自分がやらなければ」「迷惑をかけたくない」という責任感や使命感から、すべてを自分で抱え込もうとしがちです。しかし、人間には限界があります。「周りを頼ることは、決して弱さの表れではない」というメッセージを伝えることで、罪悪感なく助けを求めるきっかけを得られることがあります。この言葉は、孤立しがちな介護者に対し、あなたは一人ではないという安心感を与える重要な一言になります。
最後に
介護疲れは、誰にでも起こりうる非常に深刻な問題です。介護を頑張っている人にかける言葉は、その人の心を癒す薬にも、深く傷つける刃にもなり得ます。
「言ってはいけない言葉」を知ることは、介護者の心をこれ以上傷つけないための第一歩です。そして、「寄り添う言葉」を選ぶことで、介護者の孤独感を和らげ、精神的な支えとなることができます。
もしあなたの周りに介護をされている方がいたら、今日からぜひ、彼らの心に寄り添う温かい言葉をかけてみてください。

