
介護は終わりが見えづらく、「もう限界かもしれない…」と感じる瞬間があるかもしれません。介護者の休息は、介護を続ける上で最も重要な要素の一つです。
この記事では、元ケアマネとしての経験から、介護保険制度を最大限に活用して「介護から離れる時間」を確保するための具体的な方法をお伝えします。
なぜ介護者の休息が重要なのか?
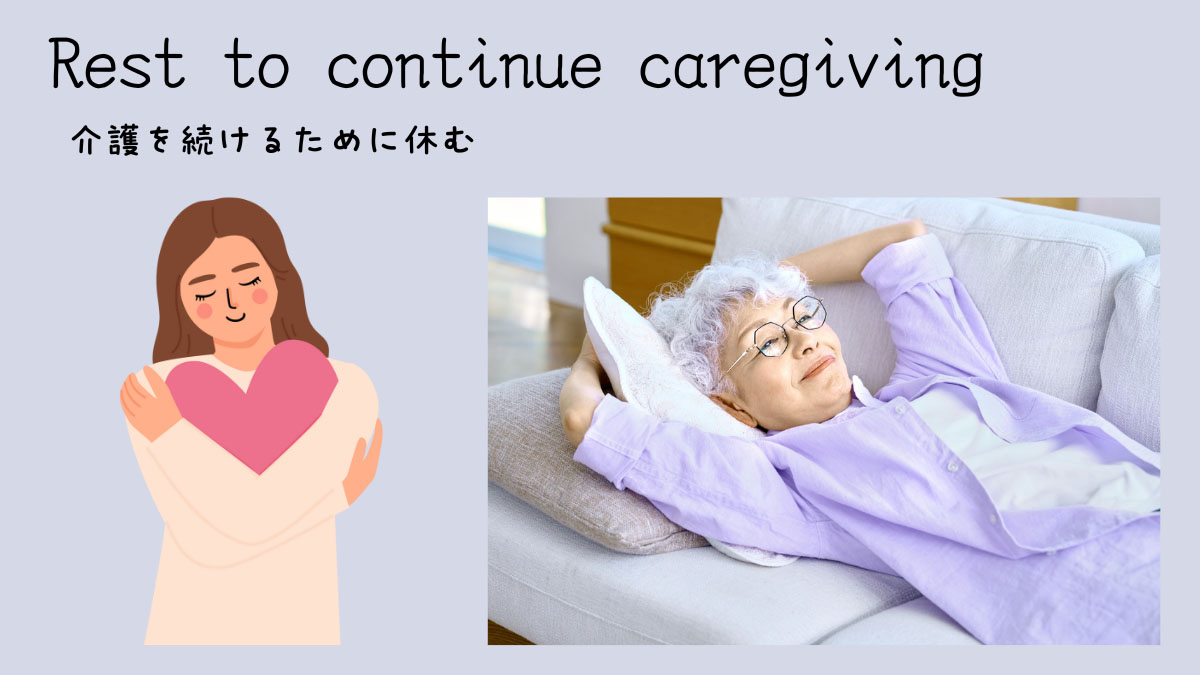
介護は終わりが見えづらい長期戦です。家族を思う気持ちが強いほど、つい頑張りすぎてしまいがちですが、介護者が心身ともに疲れ果ててしまっては、介護そのものが立ち行かなくなってしまいます。
休息不足が招く心身への影響
ケアマネジャーとして多くのご家族と関わる中で、介護者の休息が不足すると、次のような問題が起こりやすいのを何度も目の当たりにしてきました。
- 体調の悪化
睡眠不足やストレスがたまり、体調を崩しやすくなるほか、心身ともに疲労が蓄積します。
- 介護の質の低下
冷静な判断ができなくなったり、些細なことでイライラしたりして、本人との関係が悪化することがあります。
- 介護事故のリスク上昇
注意力が散漫になるため、介護中の転倒や事故を引き起こす危険が高まります。
- 介護うつ・燃え尽き症候群
精神的な負担から「もう何もしたくない」という状態に陥り、介護そのものが困難になるリスクがあります。
介護者の休息は「介護を続けるための大切な時間」
介護は長期にわたる道のりです。介護者が倒れてしまっては、大切な人を支えることができなくなってしまいます。
心と体を守るために休むことは、決して「怠けている」わけではありません。むしろ、これから先も介護を続けていくために、自分をケアする 「必要な時間」 だと考えてください。
時には、介護から少し離れる時間を持つことが、お互いにとってより良い関係を築くことにつながります。
制度を活用して「自分の時間」を確保する具体的な方法
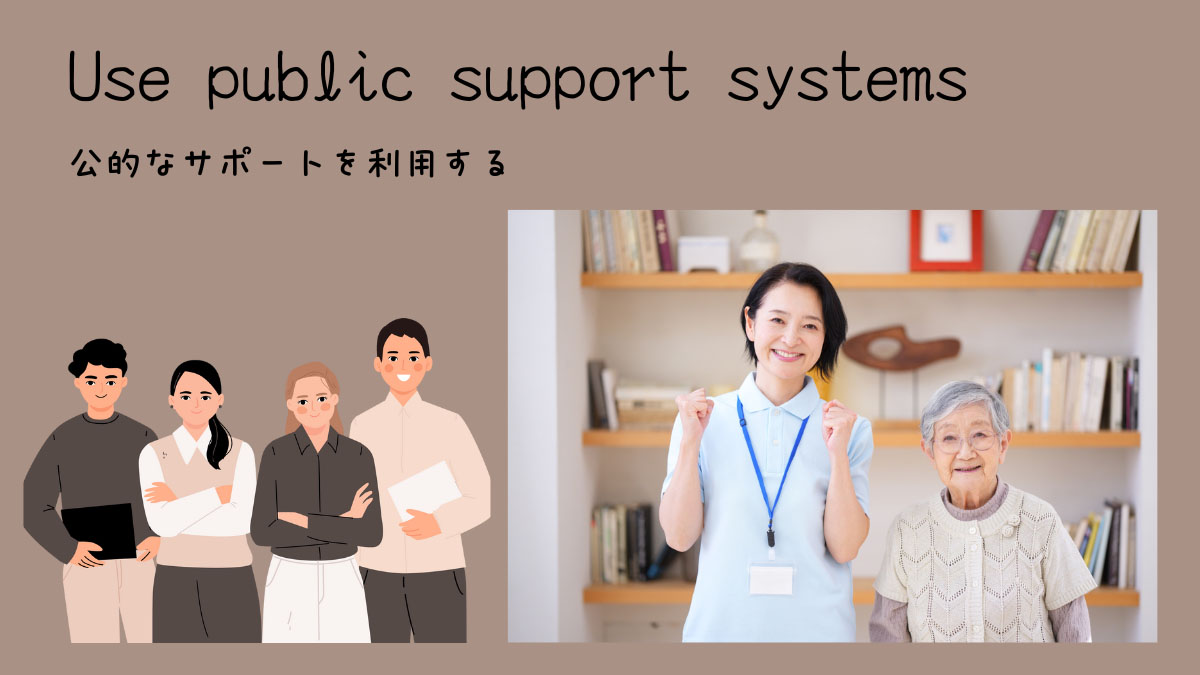
「休みたい」と思っても、介護保険でどこまで許されるのか、どうやってサービスを増やせばいいのか分からない方も多いでしょう。ここでは、具体的なサービス活用法をご紹介します。
1. ショートステイの活用法
ショートステイとは、介護が必要な方が短期間施設に宿泊し、日常生活上の支援や機能訓練などを受けられるサービスです。
介護から物理的に離れる時間を確保する上で最も有効なサービスですが、「申し訳ない」「何かあったらどうしよう」と利用をためらう方も少なくありません。
【活用例】
- まずは「お試し」で
最初から何泊も利用する必要はありません。まずは日帰りや1泊2日から始めて、本人が施設に慣れる時間を作りましょう。
- 複数施設の活用
特に予約が取りにくい地域では、複数のショートステイ施設に登録しておくことをおすすめします。一つの施設にこだわらずに選択肢を広げることで、希望の日程で予約が取れる可能性が高まります。
- 定期的な利用を計画
ケアマネジャーに「月に1回、週末に利用したい」などと具体的に伝え、ケアプランに組み込んでもらいましょう。定期的に利用することで、本人も慣れ、家族の休息も確保しやすくなります。
2. デイサービスの活用法
デイサービスとは、介護が必要な方が日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどを楽しめるサービスです。
日中の時間を活用して介護者の方が休息を取るための大切なサービスですが、週に1回などの利用だけでは、十分な休息が取れないこともあります。
【活用例】
- 利用回数を増やす
介護者の疲労がピークに達していると感じたら、ケアマネジャーに相談してデイサービスの利用回数を増やすことを検討しましょう。週に2回、3回と増やすことで、定期的な休息日が確保できます。
- 長時間利用を検討
早朝から夕方まで利用できる事業所もあります。送迎時間を含めるとまとまった休息時間が確保できるため、買い物や趣味の時間など、介護から離れてリフレッシュする機会につながります。
- 異なるサービスを組み合わせる
ショートステイとデイサービスを組み合わせることで、より柔軟な休息計画を立てることができます。例えば、平日はデイサービスを利用し、月に一度はショートステイで週末の休息を確保するといった方法も可能です。
3. 訪問介護の活用法
訪問介護は、ヘルパーが自宅を訪問し、入浴や食事の介助などを通して介護者をサポートするサービスです。
しかし、短時間の利用が中心のため、まとまった休息時間を確保するのは難しいのが現状です。
【活用例】
- 家事負担軽減には自費サービス
介護保険の訪問介護は、同居家族がいる場合、家事支援(生活援助)が制限されることがあります。 家族全員分の調理や家族が使用しているスペースの掃除などを頼みたい場合は、介護保険外の自費サービスを活用すると、介護者の負担軽減につながります。
- リフレッシュするための時間を作る
介護保険の範囲では、ヘルパーに長時間の見守りを頼んで介護者が外出することは難しいとされています。しかし、自費サービスを組み合わせれば、ヘルパーが付き添う間に、介護者は買い物や趣味など、介護から離れてリフレッシュする時間を確保できます。
訪問介護事業所によっては、介護保険と自費サービスの両方を提供しているため、ケアマネジャーに相談してみることをお勧めします。
4. 制度上の「家族の休息」という位置づけ
介護保険制度は、介護者を含めた家族の生活を守るためのものです。ケアマネジャーは、ご本人の状態だけでなく、介護者の状況も考慮してケアプランを作成する義務があります。
「介護負担の軽減」や「介護者の休息確保」は、ケアプランを作成する際の重要な視点です。そのため、自分自身の希望を遠慮なく伝えることが、サービス利用への第一歩となります。
ケアマネジャーに「休みたい」と正直に伝える勇気

「休みたい」と口にするのは、まるで介護を放棄するようで言い出しにくいと感じるかもしれません。しかし、ケアマネジャーはそうは思いません。
ケアマネジャーは、「休みたい」という言葉の背景にある家族の苦労やストレスを深く理解しています。それは、怠慢や無責任ではなく、介護を続けるためのSOSだと捉えているからです。
「最近、疲れがたまっていて…」「自分の時間が全く取れなくて…」と正直に話すことで、ケアマネジャーは現状を正確に把握し、最適なサービスを提案しやすくなります。
「休むこと」は、介護の質の維持と継続のために必要不可欠なことです。ケアマネジャーは、そのための頼もしいパートナーです。一人で抱え込まず、まずは正直な気持ちを伝えてみてください。
仕事や育児との「両立者」は特に注意が必要

働きながら介護をしている方や、育児と介護を同時に行っている「ダブルケア」の負担は、想像以上に大きいものです。時間的、精神的な余裕がますます失われ、介護者の休息不足はより深刻な問題となります。
- 時間的な制約
仕事の拘束時間や子育てのタスクに追われ、介護に割ける時間が限られます。結果として、介護の負担が一点に集中し、休む時間が全くなくなってしまうことがあります。
- 精神的なプレッシャー
職場での責任や子育ての悩み、そして介護の心配が同時に押し寄せ、常に緊張状態が続きます。これにより、ストレスが蓄積し、心身の不調を引き起こしやすくなります。
仕事と介護の両立やダブルケアの場合、一人で全てを抱え込むことは非常に危険です。介護保険サービスに加え、職場や地域の相談窓口、そして何より家族に状況を伝え、助けを求めることが重要です。
最後に
介護は、誰にとっても初めての経験であり、先の見えない不安や孤独を感じることもあるでしょう。しかし、あなた一人で全てを背負い込む必要はありません。
今回紹介した介護保険サービスや自費のサービスは、介護者の負担を軽減し、心と体を守るために存在しています。ケアマネジャーや周囲の人々を頼ることは、決して弱さではなく、介護を長く続けるための賢明な選択です。
「休みたい」という気持ちを大切にしてください。あなたの休息は、被介護者である大切な人のためにもなります。一人で悩まず、まずは一歩踏み出して、私たちケアマネジャーにご相談ください。


