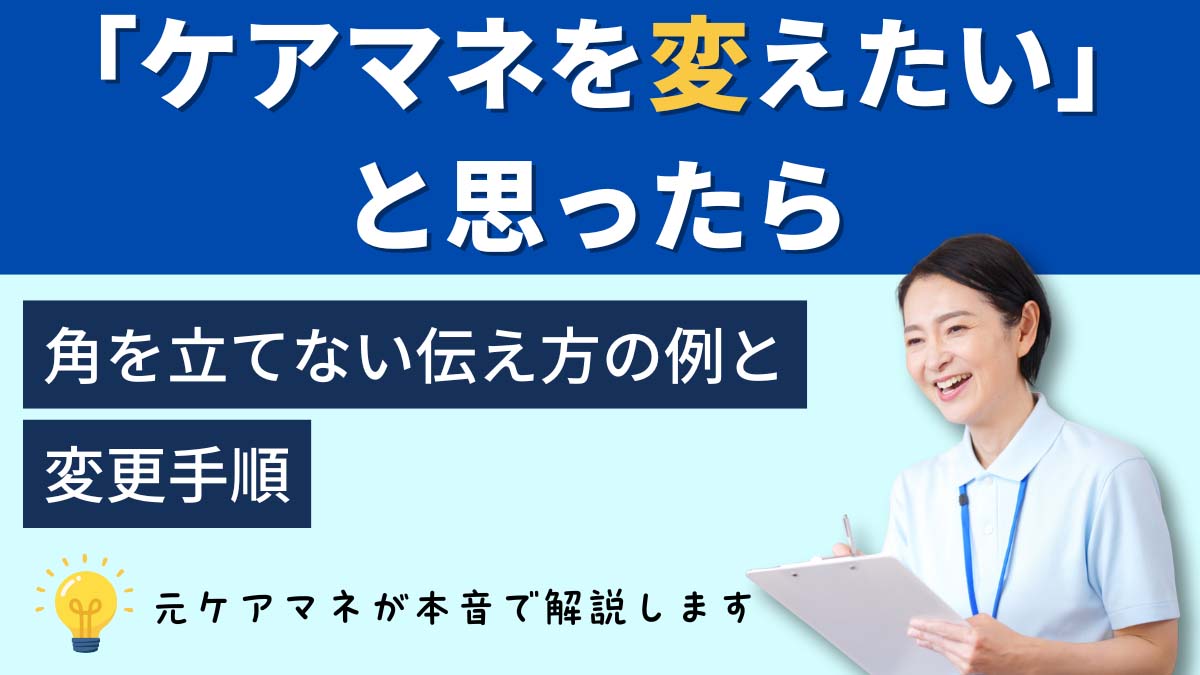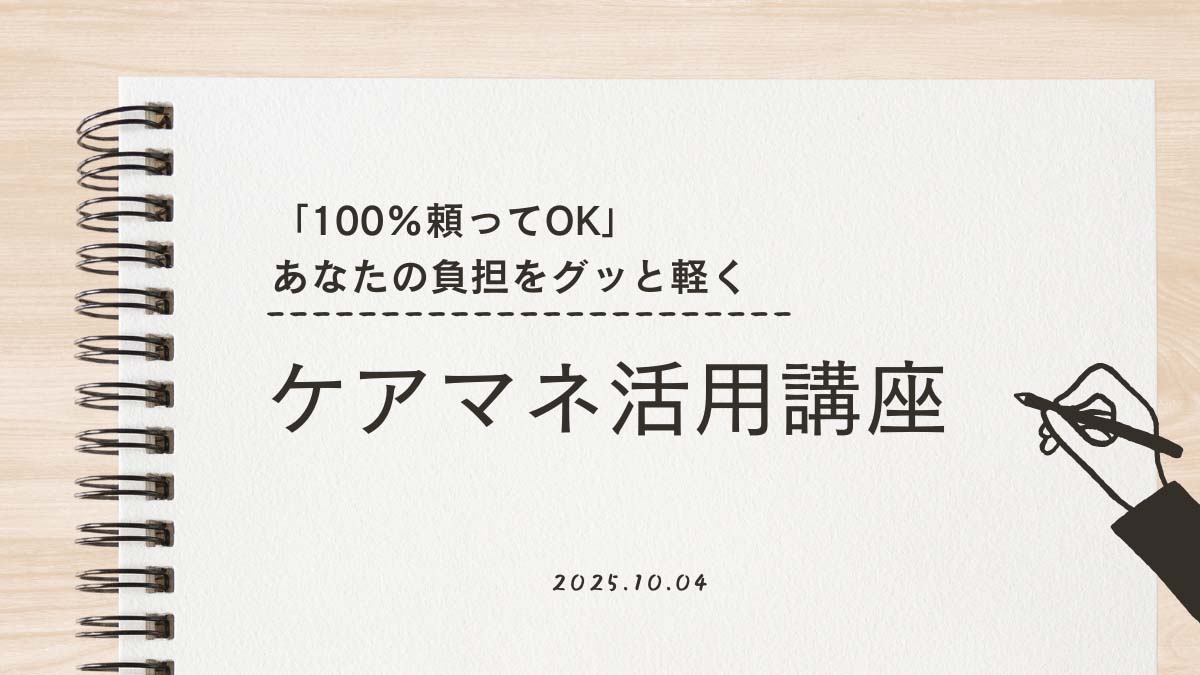
「ケアマネジャーに何を頼めばいいか分からない」「要望がうまく伝わらない」。介護の負担を一人で抱え込み、そう感じていませんか?
ケアマネジャーは単なる介護サービスの窓口ではありません。その役割と活用のコツを知ることで、あなたの介護生活は劇的に変わります。14年の現場経験を持つケアマネジャーである私が、介護の専門家を最大限に活用するための「使い倒し方」を、具体的な6つのコツとしてお伝えします。
この記事を読み終える頃には、あなたが抱える介護の悩みをケアマネジャーと一緒に解決できる、頼もしいパートナーシップを築くヒントが見つかっているはずです。
ケアマネは「何でも屋」じゃない|その役割と限界を理解する

多くの家族がケアマネジャーに期待しすぎるあまり、ミスマッチが生じることがあります。ケアマネジャーは介護保険制度の専門家であり、あくまで本人と家族の生活課題を整理し、適切なサービスをつなぐ役割を担っています。
ケアマネジャーができないこと
ケアマネジャーは日々、様々な相談を受けますが、中には私たちの役割を超えるものも残念ながら存在します。
事例1:深夜の緊急相談
「もう、やってられない!何度言っても父が言うことを聞かないんです。もう、どうすればいいか分かりません…」と、深夜に電話がかかってきたことがあります。この時、電話の主は介護の悩みや不安を抱え、行き場のない感情をぶつける場所としてケアマネジャーに連絡してきました。しかし、私たちはご家族の精神的な支えになることはできますが、深夜に個人的な相談に対応することはできません。
次の日に、夜中でも利用できる介護者向けの相談窓口や家族会などの存在を伝え、介護負担を軽減するため、ショートステイ(短期入所)やデイサービスを増やす提案も行いました。
事例2:通院の代行依頼
「仕事でどうしても通院に付き添えないから、代わりに病院に連れて行ってくれませんか?」と頼まれたこともあります。ケアマネジャーは介護サービス計画の立案と調整が主な仕事であり、情報連携のための同席はしますが、通院介助はできません。このような場合、私たちは介護タクシーや通院介助サービス(介護保険サービス外の自費サービスを含む)を紹介し、通院がスムーズに行えるよう手配をサポートします。
このように、ケアマネジャーは医療行為や身体介護そのもの、金銭的な援助、24時間365日の緊急対応はできません。あくまで介護サービス計画(ケアプラン)を立て、サービス事業所と連携することが仕事です。
ケアマネジャーができること
介護保険サービスだけでなく、医療機関や自治体の独自サービス、ボランティア団体、民間サービスなど、幅広い社会資源の中から最適なものを提案できます。
また、医療と介護の連携もケアマネジャーの重要な役割です。ご本人の病状や体調の変化を医療従事者と共有し、主治医や訪問看護師と協力してケアプランに反映させます。
さらに、要介護者・要支援者だけでなく、介護をされているご家族の課題解決もケアプランに盛り込むことができます。
この「役割と限界」を理解することが、良い連携の第一歩です。
【ケアマネジャーの業務内容】
| 業務カテゴリー | 業務内容の詳細 | 家族にとってのメリット |
|---|---|---|
| アセスメント | 本人と家族の生活状況、心身の状態、抱えている課題や要望をヒアリングし、情報を収集します。 | 漠然とした不安や介護疲れを、具体的な「困りごと」として整理する手伝いをしてもらえます。 |
| ケアプラン作成 | アセスメントで得た情報に基づき、適切な介護サービスを組み合わせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。 | 専門的な知識がなくても、ご本人の状態に合った最適なサービスの組み合わせを提案してもらえ、「何をすればいいか」が明確になります。 |
| サービス調整 | ケアプランに沿って、介護事業所や医療機関と連携を取り、サービス利用の手配や日程調整を行います。 | 家族が一つひとつ事業所を探したり、連絡したりする負担がなくなり、手配の手間が省けます。 |
| モニタリング | ケアプラン開始後も、定期的にご本人やご家族と面談し、サービス利用状況や効果を確認します。 | 本人や家族の状況が変わった時に、すぐにケアプランを見直してもらい、最適な支援を継続できます。常に状況を見直してもらえます。 |
| 情報提供・相談 | 介護保険制度や地域サービス、各種福祉制度に関する情報を提供します。ご家族が抱える介護の悩みや不安について相談を受け、助言やサポートを行います。 | 介護保険以外の制度や、知られていない地域の支援策など、必要な情報を教えてもらえるため、一人で悩まずに済みます。 |
| 給付管理 | 介護サービス利用にかかる費用を計算し、介護保険から給付される費用を国民健康保険団体連合会に請求します。 | 介護保険の給付管理は複雑な計算や請求手続きが必要ですが、ケアマネジャーがすべて代行してくれるため、家族が面倒な書類作成や計算を行う必要はありません。 |
ケアマネを「使い倒す」ための6つのコツ
ケアマネジャーの役割を理解したら、次は実践です。本人と家族、両方にとって最適な介護を実現するため、ケアマネジャーを最大限に活用するための具体的なコツを6つご紹介します。
コツ1:困り事は「具体的に、すべて」伝える

多くの家族は「疲れた」「大変だ」と漠然とした悩みを抱えています。しかし、その言葉だけでは、ケアマネジャーが適切な支援につなげるのが難しくなってしまいます。漠然とした悩みは、具体的な「困りごと」に変換して伝えてください。
例えば、「疲れた」の背景にあるものを分解してみると、解決策が見えてきます。
【具体的な原因の例】
- 夜間の見守りで眠れず、睡眠不足になっている
- 食事に時間がかかりすぎて、自分の時間が全くない
- 仕事と介護の両立が厳しくなってきた
【ケアマネジャーが提案できる解決策の例】
- 夜間の訪問サービス
- 食事介助に特化したヘルパー派遣
- レスパイト(介護者の休息)を目的としたショートステイの利用
このように、具体的な情報を共有することで、より的確で効果的なサポートを引き出すことができます。
コツ2:サービス担当者会議は「主役」として参加する

ケアプラン作成後に行われるサービス担当者会議は、単にケアプランを承認する場ではありません。この会議は、ケアマネジャーと、介護サービスを提供するヘルパーやデイサービス職員、場合によっては医師やリハビリ専門職といった多職種のプロが一堂に会する貴重な場で、介護のプロ集団を「使い倒す」ための、最大のチャンスです。
この場で遠慮して発言しないと、「こんなはずじゃなかった」と後で後悔することになりかねません。積極的に意見を述べることで、介護のプロたちを動かし、ご本人とご家族、両方にとって最適なケアプランを作り上げることができます。
会議を最大限に活用するために、次の点を意識してください。
- 疑問点や意見を率直に言う
提案されたサービス内容に少しでも不安や疑問があれば、その場で質問して解消しましょう。「このサービスは本当に必要なのか」といった率直な意見も遠慮せずに伝えてください。
- 本人の様子を再確認する
事前にケアマネジャーに伝えた内容に加え、自宅での本人の様子や最近の変化など、プロのチーム全員で認識を共有し、ズレがないか確認しましょう。
- 家族の要望を明確に発言する
「家族の休息」の必要性や、「少しでも自分でできることを増やしてほしい」といった要望をはっきりと伝えることで、プロのチームがあなたのために動くきっかけを作ります。
コツ3:「隠れた要望」も共有する

介護は、ただ日常生活の動作を支えるだけではありません。本人と家族の生活の質(QOL)を高めることも、ケアプランの重要な目的です。
【本人の要望例】以前から大切にしている趣味や、これから挑戦したいことなどを伝えてください。
- 「できるだけ自分で料理や買い物をしたい」
- 「昔から続けている俳句の会にまた参加したい」
- 「近所の公民館で開かれるカラオケサークルに、もう一度行ってみたい」
- 「自分で飼っているペットの世話だけは、最後まで自分でしたい」
こうした希望を共有することで、より本人の意欲を引き出すケアプランにつながります。
【家族の要望例】家族が介護を通じて諦めていることや、ストレスに感じていることも伝えてください。
- 「仕事と介護の両立が厳しい」
- 「夫婦でゆっくり外食する時間を作りたい」
- 「介護から離れて、一人で買い物や美容院に行く時間を作りたい」
- 「兄弟間で介護の負担が偏っている現状を改善したい」
このように、家族自身の生活の要望も重要な情報です。
コツ4:本人の「人となり」を伝える
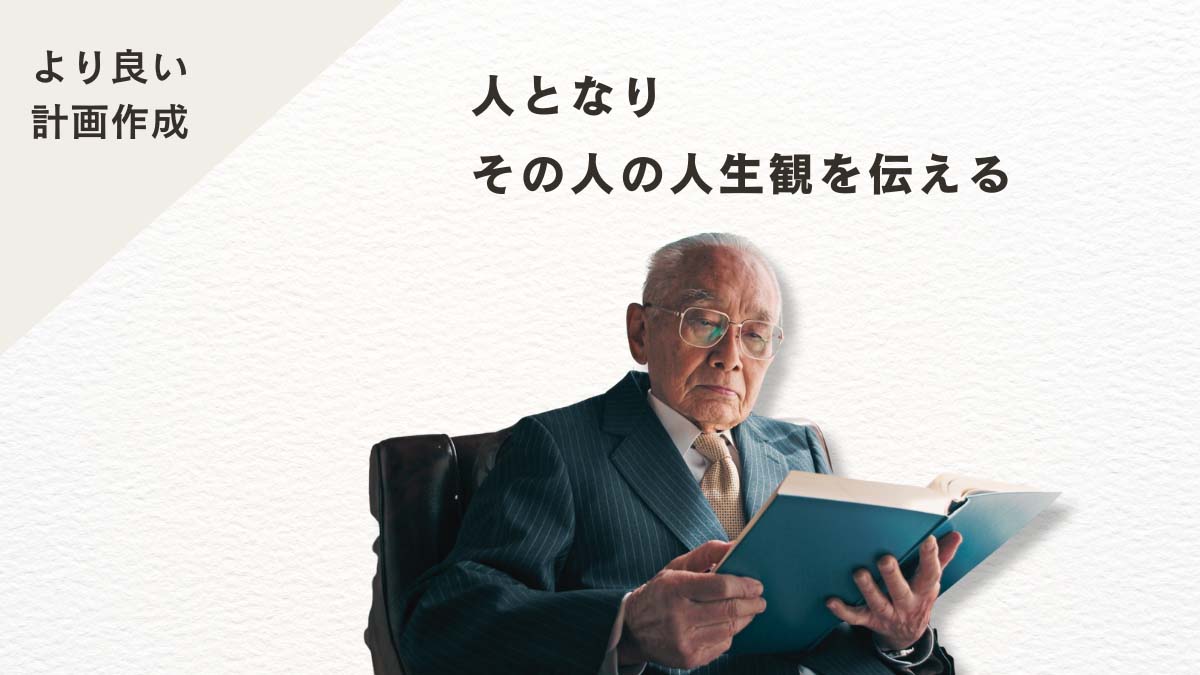
介護は、その場の苦労や問題に焦点が当たりがちです。しかし、本人の「人となり」をケアマネジャーに伝えることは、その人を深く理解し、より本人が受け入れやすい、心に寄り添ったプランを立てる上で非常に重要です。特に認知症の方の場合、ケアの糸口を見つける上で欠かせない情報となります。
【伝えるべき「人となり」の例】
- 過去の仕事や役割:何を専門にしてきたか、どんな責任を担ってきたか
- 趣味や好きなこと:没頭できることや、楽しんできたことは何か
- 性格や人柄:どんな性格か(例: 社交的か、職人気質か)、人との関わり方の傾向
- 得意なこと:自分でできることや、自信を持っていることは何か
- 大切にしている習慣:朝の日課や、毎日欠かさず行っていることなど
こうした情報があることで、ケアマネジャーは単なる介護サービスだけでなく、本人の生きがいにつながるような個別性の高いケアプランを提案できます。
コツ5:連絡ツールを使い分ける
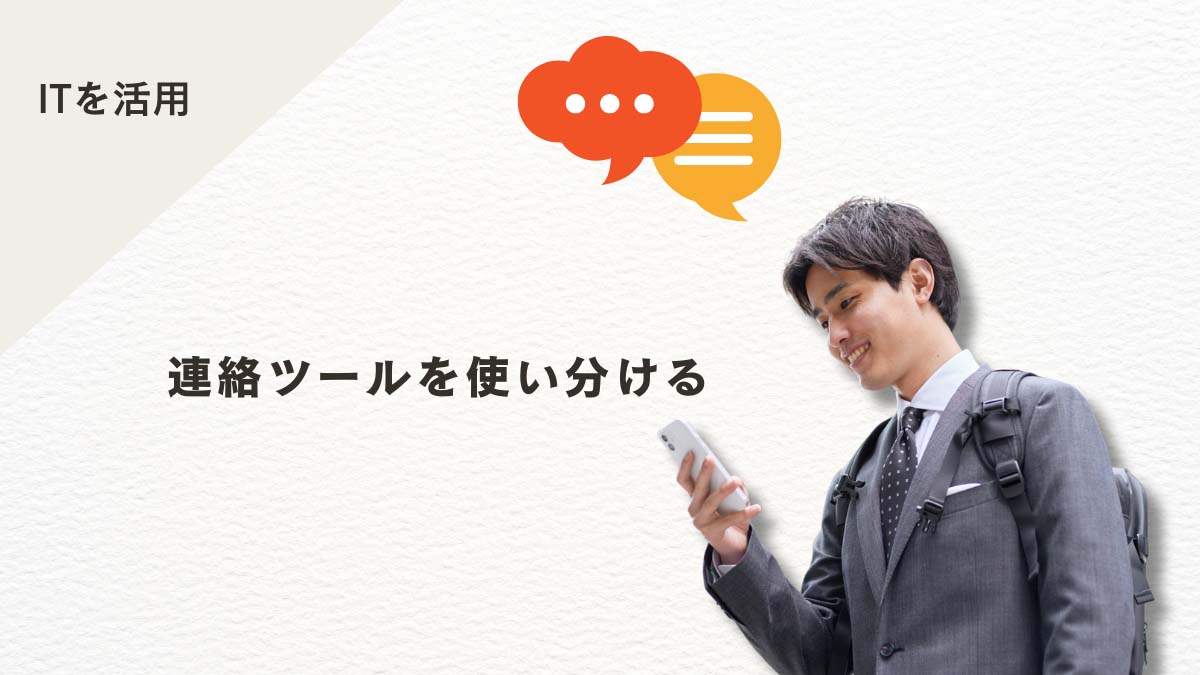
担当ケアマネジャーとの連絡には、電話以外のツールも検討してみましょう。メールやSNSなどのコミュニケーションツールは記録が残り、連絡の行き違いや抜け漏れを防げるという大きなメリットがあります。
【メール・SNSが向いている内容】
- 確認事項:サービス利用の日程や時間、金額など、正確な情報が必要なとき
- 共有したい情報:病院の検査結果や診断書、新しく購入した福祉用具の情報など、文章や写真で伝えた方が分かりやすいとき
- 一般的な相談:「〇〇というサービスは利用できますか?」といった、すぐに返答が必要でない質問
【電話・対面が向いている内容】
- 感情的な悩み:「介護が辛い」「将来が不安」といった、気持ちを伝えたいとき。文章では伝わりにくいニュアンスや、声の調子で心の状態を汲み取ってもらえます。
- 緊急性の高い相談:本人の体調が急変したときや、早急な対応が必要なとき。
- 複雑な相談:複数の課題が絡み合っている場合など、対話を通して整理したいとき。
「こんなことで連絡していいのかな」とためらう必要はありません。早い段階で情報を共有することで、大きなトラブルを未然に防げる可能性が高まります。例えば、本人の体調不良を早めに相談すれば、かかりつけ医と連携して受診を促すなど、適切な対応をすぐに取ることができます。
コツ6:分からないことは何でも聞く

介護保険制度は複雑で、聞き慣れない専門用語も多いです。わからないことをそのままにしておくと、不必要なサービスを利用したり、本当に必要な支援を見過ごしたりする可能性があります。ケアマネジャーは介護の専門家です。 遠慮せずに、分からないことは何でも聞いてください。
- 専門用語の確認:「モニタリング」や「レスパイト」、「多職種連携」など、ケアマネジャーが使う専門用語の意味が分からなければ、その都度確認しましょう。
- 制度の仕組みについて:「ケアプランはどうやって決まるの?」「介護保険の自己負担額はどのくらい?」といった、制度の仕組みに関する疑問も遠慮なく質問してください。
- サービスの具体的な内容:「〇〇というデイサービスでは、具体的にどんな活動をするの?」「リハビリはどのくらい効果があるの?」など、サービスの具体的な内容を聞いて、本人が本当に楽しめるかどうか、効果があるかどうかを判断しましょう。
疑問点を一つひとつ解消することで、納得して介護サービスを利用できるようになり、ケアマネジャーとの信頼関係も深まります。
最後に
良いケアマネジャーは、家族の「よき伴走者」です。一人で抱え込まず、遠慮なく私たちを「使い倒して」ください。それは、結果的に家族の介護生活をより良いものにするための、最も賢い選択なのです。