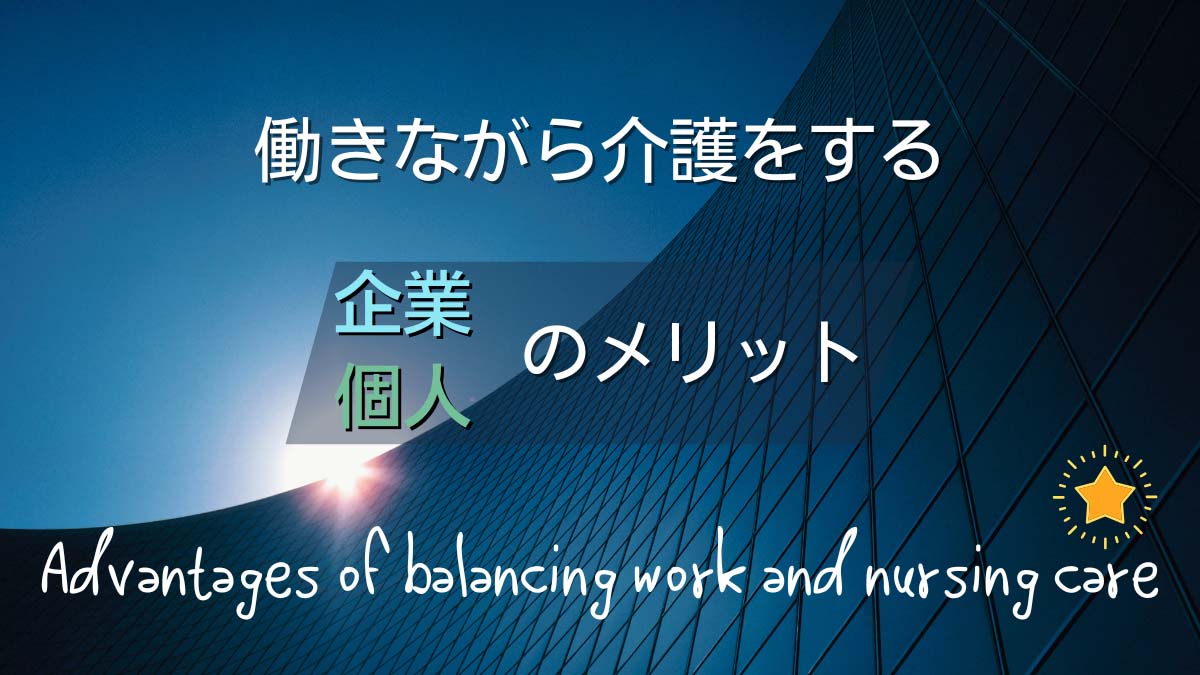元気だった親が突然病気やケガ、認知症などで介護が必要になったとき、どう対処すればよいでしょうか。戸惑うことが多く、特に介護者が仕事をしている状況では、限られた時間の中で何とか解決策を見つける必要があります。
今回は、仕事と介護を両立する上で避けるべき行動を具体例とともにまとめました。仕事と介護のある生活を維持するために、必要な情報を集めておくことが重要です。
今回は仕事と介護を両立する上でやってはいけないことを、事例とともにまとめました。
これはNG①:介護をやりすぎてしまう
親に介護が必要になった際、「いい機会だから親孝行をしよう」という気持ちになることがあります。しかし、親を大切にしすぎると思わぬ結果を招くことがあります。
ケース1
高齢の母親が肺炎で入院し、退院後に日常生活の一部でサポートが必要となりました。息子のAさんは親孝行の気持ちから、10日間仕事を休み、家事全般を引き受けながら、母親が安静に過ごせるよう心がけて介護を行いました。
しかし1週間後、母親はトイレに行く距離も歩けなくなり、車いす生活に。これにより介護の負担が増え、Aさんは職場復帰の目途が立たなくなりました。
大切にしすぎることで筋力が低下する
筋肉の伸縮が行われない寝たきりの状態では、1週間で約3~5%、2週間で約10%の筋力が低下すると言われています。さらに、筋力だけでなく関節の動きも悪化し、全身の機能が低下する悪循環が生じます。
ケース1の場合
Aさんの適切な介護方法は、母親のできない部分のみをサポートし、それも徐々に減らしていくことでした。介護保険サービスを活用してデイサービスなどに通い、回復と悪化の予防を図ることが重要です。
「親の介護はやりすぎない」が重要なポイントです。親の自立を促すためには、できる範囲でサポートを行い、必要に応じて介護の専門職に任せることが大切です。また、介護者自身も無理をせず、負担を減らしながら取り組むことを心がけましょう。

これはNG②:仕事を長期間休み、介護に専念する
介護のために長期休暇をとると、職場復帰が困難になり、経済的負担も増加する可能性があります。
ケース2
Bさんは久しぶりに帰省した際、両親の生活がうまくいっていないことに気づきました。母親は認知症を発症し、父親も体調を崩しており、家の中はゴミが散乱している状態でした。Bさんは長期休暇をとり介護に専念しましたが、両親が介護保険サービスを拒否し、介護から抜け出せなくなりました。その結果、仕事復帰ができず、プロジェクトから外されることになりました。
介護のために長期休暇を取るのはNG
長期間の介護に専念すると、以下の問題が生じる可能性があります。
- 親が家族に依存する:長期的な家族介護は依存を引き起こし、介護者がいないと生活できなくなる恐れがあります。
- 介護保険サービス導入のタイミングが遅れる:家族が介護に専念すると、「身内の介護の方が良い」と考え、介護保険サービスの利用を拒む場合があります。その結果、体を動かす機会が減り、症状が悪化しやすくなり、回復のチャンスを失う恐れがあります。
- 介護者自身が仕事に復帰しづらくなる:介護から抜け出せない状況が続くと、職場復帰が難しくなり、介護離職のリスクが高まります。
これらの理由から、介護のために長期休暇を取るのは避け、早いタイミングで介護保険サービスを利用しながら、仕事と介護を両立させることが重要です。
ケース2の場合
Bさんは帰省して異変に気づいた段階で、地域包括支援センターに相談する必要がありました。早期に介護保険サービスを導入し、ケアマネジャーと協力して適切な支援を受けることで、両親の生活を安定させることが可能です。また、介護保険サービスを拒まれた場合は、ケアマネジャーや介護サービス関係者に説得を依頼するのも有効な手段です。
Bさん自身は早めに職場へ復帰し、上司や人事部と相談しながら「介護休暇」や「介護休業」などの制度を計画的に活用することが重要です。これにより、仕事と介護を両立できる体制を整えることができます。
介護と仕事を両立させるには、早めに適切な支援を受けることが欠かせません。計画的に介護保険サービスを利用し、周囲の協力を得ながらバランスを保つことで、介護者自身の心身の健康を守ることにもつながります。

これはNG③:リモートワークの落とし穴
リモートワークは介護を両立する方法の一つですが、仕事と介護の境界線が曖昧になり、実際には多くの問題を引き起こすことがあります。
ケース3
Cさんはリモートワークをしながら認知症の父親を介護していました。しかし、仕事中に父親が徘徊したり、危険な行動への対応に追われることが多く、仕事と介護を両立するのが困難でした。その結果、Cさんは心身ともに疲れてしまい、体調を崩してしまいました。
境界線の曖昧さ
リモートワークでは、常に介護ができる体制になりがちです。その結果、頻繁に仕事を中断する必要が生じ、集中が難しくなります。これにより、仕事の効率が低下し、最終的にはパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。
さらに、仕事と介護の境界が曖昧になることで、どちらにも十分な力を注ぐことが難しくなります。この状況は精神的なストレスを増大させ、長期的には健康に悪影響を与える可能性があります。
ケース3の場合
仕事と介護を両立するためには、適切な支援を受けながらバランスを取ることが大切です。Cさんはリモートワーク中に認知症の父親の介護を直接行うのではなく、介護保険サービスを活用することが必要でした。これにより、介護の質を保ちながら、仕事に集中できる環境を整えることができます。特にデイサービスを利用すれば、送迎があるため安心で、約5~6時間ほど介護から解放される時間を確保できます。
リモートワークは、仕事と介護を両立させるために導入する企業が増えています。しかし、常に介護ができる環境になることで、かえって介護負担や精神的なストレスが増加することもあります。そのため、リモートワークを活用する場合でも、介護保険サービスを積極的に利用し、適切な距離を保つことが大切です。

考え方を変える・見方を変える
仕事と介護を両立するためには、考え方や視点を柔軟に変えることが不可欠です。現在の人口構造の変化により、50年前の介護の考え方は今の時代には適応しづらくなっています。そのため、時代に合った新しい考え方を取り入れることが求められます。ここでは、仕事と介護を両立させるために役立つ「新しい視点」をご紹介します。
出社はレスパイトになる
出社することは、介護から一時的に解放される大切な休息(レスパイト)の時間になります。職場で仕事に集中することでリフレッシュでき、心身の負担を軽くする効果も期待できます。また、仕事仲間との会話や友人とのランチを楽しむことで、自分の時間を大切にする機会にもなります。
出社中は、デイサービスなどの介護保険サービスを利用して、介護を専門家に任せるのがおすすめです。これにより、安心して仕事に専念できる環境を整えることができます。
介護をプロジェクトとして考える
介護をプロジェクトとして捉えることで、計画的かつ効率的に進めることができます。まず、ケアマネジャーや介護の専門家と連携し、目標を明確にしましょう。役割分担を行い、定期的に進捗を確認することで、状況に応じた適切な対応が可能になります。
また、デイサービスや訪問介護を活用して「介護をアウトソーシング」することで、負担を軽減できます。家族内で役割を分担し、直接介護に関われない家族には金銭面での支援をお願いするなど、柔軟な考え方が重要です。
さらに、時間管理やプロジェクトマネジメントの手法を取り入れることで、仕事と介護のバランスをより効果的に整えられます。このように、計画的なアプローチと専門家の力を借りることで、負担を減らしながら効率的な介護が可能になります。

介護で親孝行はしない
現代では高齢者を支える側が減少しているため、家族だけで介護を行うのは現実的ではありません。親孝行の気持ちから過度に介護をすると、介護者の負担が増し、親の自立を妨げるだけでなく、仕事との両立も難しくなります。
「介護は家族がやるべき」「介護は育ててもらった恩返し」「介護は親孝行だ」といった考え方は、現役世代10人で1人の高齢者を支えていた約50年前の時代のものです。しかし、現在では約2人で1人の高齢者を支えている状況となり、「介護は親孝行」という考え方は現実にそぐわなくなっています。
親孝行は愛情や感謝の気持ちを示す形で行い、食事や会話を楽しむなど、一緒に過ごす時間を大切にすることに重点を置きましょう。
まとめ
仕事と介護を両立させるには、過度な介護を避けること、介護のために長期休暇を取らないこと、そしてリモートワークでの介護の限界を理解することが大切です。
また、介護に対する考え方を今の時代にアップデートし、新しい視点を持つことも欠かせません。適切な支援を受け入れ、効率的な介護方法を取り入れることで、仕事と介護のバランスを上手に保つことが可能になります。