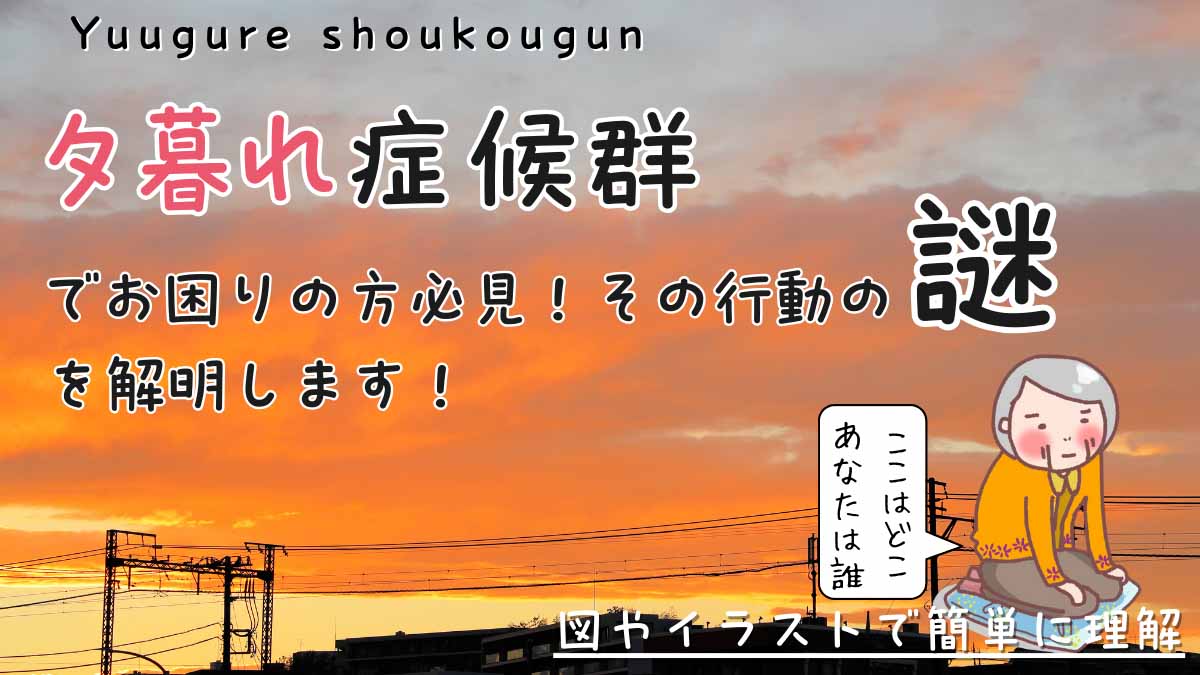認知症の家族が一人で外に出て行方不明になった場合、介護者は大きな不安に襲われます。しかし、適切な知識と準備があれば、万が一の事態にも落ち着いて対応でき、本人を早期に発見できる可能性が高まります。
この記事では、認知症の家族が行方不明になった際の具体的な対応方法や、日頃からできる予防策について解説します。
認知症の家族が行方不明になったら最初にしてほしい3つのステップ

認知症の家族が行方不明になったと気づいたら、まずは冷静になることが何よりも重要です。パニックにならず、以下のステップで行動しましょう。
ステップ1:家と近所をすぐに探す(最初の15〜20分)
まず、自宅の中やその周辺を落ち着いて探してみましょう。納戸や庭の隅、物陰など、普段はあまり入らないような場所にいることもあります。また、本人がよく立ち寄る場所(近所のコンビニや公園、知人の家など)に足を運んだり、連絡を取ったりすることも有効です。
ステップ2:迷わず警察に通報する
15〜20分探しても見つからない場合は、ためらわずに最寄りの警察署や交番に連絡しましょう。行方不明から時間が経つほど捜索範囲が広がり、発見が難しくなります。迅速な初動が早期発見の鍵です。
通報や行方不明者届の提出時には、できるだけ多くの情報を伝えられるように、事前に以下についてリストアップしておくとスムーズです。
- 本人の身体的特徴:氏名、年齢、身長、体重、顔の特徴、持病など
- 当日の状況:いなくなったときの服装、靴、持ち物(財布、鍵など)
- 最終目撃情報:最後にどこで、何時頃、どんな状況で見かけたか
- 過去の情報:昔住んでいた場所、過去の職場、よく通る散歩ルートなど
- 本人の写真:直近で撮影した顔がはっきりとわかる写真
【警察が早期通報を推奨する理由】
- 早期発見・保護の可能性を高める
警察庁の統計によると、認知症による行方不明者は年々増加傾向にあり、時間の経過とともに発見が困難になります。警察は、迅速な捜索開始が本人の安全を確保する上で最も重要であると考えています。
- 「特異行方不明者」としての対応
認知症などにより自力で帰宅できない可能性のある行方不明者は、「特異行方不明者」として扱われます。これにより、警察は通常の行方不明捜索よりも優先的に、より広範囲で大規模な捜索を行う体制を取ることができます。
- 地域との連携
多くの警察本部や自治体は、見守りネットワークやSOSネットワークを構築し、行方不明者の情報を地域全体で共有しています。早期に通報することで、これらのネットワークが起動し、連携した捜索活動が可能になります。
ステップ3:地域のネットワークに協力を依頼する
警察への通報と同時に、地域包括支援センターやケアマネジャー、利用中の介護サービス事業所に連絡し、協力を仰ぎましょう。事前に見守りネットワークやSOSネットワークに登録している場合は、その旨を伝えて情報を共有してもらうことが重要です。
日頃から近隣住民に顔を覚えてもらい、「いざという時は見かけたら連絡してほしい」と協力をお願いしておくことも、緊急時に大きな助けとなります。
万一に備える「日頃の予防策」

行方不明のリスクを減らすためには、日頃からの備えが非常に重要です。体調管理と物理的な対策を組み合わせ、安全な環境を整えましょう。
体調管理が「備え」になる理由
家を出て行ってしまう行動の背景には理由があり、その気持ちに寄り添い、傾聴することが大切だとされています。しかし、何よりも優先すべきは水分と便秘の管理です。これらは認知機能と密接に関わっており、外へ出ようとする直接的な引き金となる可能性があるからです。
- 水分
体内の水分量が減少すると、血液が濃くなり、脳への酸素供給が低下します。これにより、認知機能がさらに低下しやすくなります。
- 便秘
便秘は、直腸に便が停滞することで交感神経を刺激し、精神的な落ち着きを失わせます。この不快感やイライラが、外へ向かう行動を誘発することがあります。
水分不足や便秘による身体の不調が続くと、本人は「今いる場所がわからない」「どうすればいいかわからない」といった、状況を認知したり判断したりすることが困難になります。結果として、家から出て行ったり、知っているはずの道が分からなくなってしまうのです。
したがって、認知症の方を介護する際は、意識的に水分補給と便秘の解消を心がけることが、何よりも優先されるべき「事前の備え」となります。日頃から体調を良好に保つことは、認知機能そのものの維持にもつながる重要な予防策です。
物理的・技術的な備え
家を出て行ってしまう行動を物理的に管理し、万が一の事態に備えるためのツールも活用しましょう。
1. 身元証明の徹底
外で保護された際に身元がすぐにわかるように、衣服や持ち物の内側に見えにくい形で名前、住所、緊急連絡先を記載しておきましょう。アイロンプリントやQRコード®付きの迷子札、見守りシールなども有効です。
2. GPS見守り機器の活用
GPSは、もしもの時に本人の位置をリアルタイムで特定できるため、早期発見に非常に有効です。さまざまなタイプがあるので、本人の性格や生活習慣に合ったものを選びましょう。
| 端末の種類 | 特徴 | 費用(参考) |
|---|---|---|
| 靴型 | 靴に内蔵されているため、紛失や持ち忘れの心配がない。 | 購入:1万円前後、レンタル:月額3,000円程度 |
| ストラップ・キーホルダー型 | 軽量でバッグなどに取り付け可能。 | 本体価格:5,000円前後、月額通信費:500円前後 |
| スマートウォッチ型 | 見た目は普通の時計。GPS追跡に加え、転倒検知など高機能なものもある。 | 数千円から数万円 |
多くの自治体で、認知症高齢者向けのGPS機器の貸与や利用料の補助制度があります。お住まいの自治体窓口(地域包括支援センターなど)やケアマネジャーに相談してみましょう。
3.センサーやカメラによる見守り
センサーやカメラを活用して、見守りを行うこともできます。
- センサー設置
玄関や窓に人感センサーや開閉センサーを設置することで、本人が外に出ようとしたことをすぐにスマートフォンに通知してくれます。
- 見守りカメラ
室内や玄関に設置した見守りカメラは、離れた場所にいても自宅の様子を確認できるだけでなく、機種によっては双方向の通話機能を備えているものもあります。もし本人が外に出ようとしていても、落ち着いて声をかけることで行動を制止できる場合があります。
4. 地域の公的支援とネットワーク
個人の備えに加えて、地域全体で認知症の方を支える「共助の仕組み」を活用することで、より強固な安全網を築くことができます。
- 自治体の見守りネットワーク
多くの自治体が見守りネットワークやSOSネットワークを整備しています。事前に本人の情報を登録しておくことで、万が一の際に警察や関係機関に情報が迅速に共有されます。
- 地域との連携
近隣の協力事業所や住民に、行方不明者の情報をメールで一斉配信するサービスを提供している自治体もあります。
家族が一人で抱え込まないために

介護の重圧は、精神的・物理的な負担を増大させ、一人で抱え込むと孤立を招くことがあります。もしもの事態への不安だけでなく、介護全般の様々な悩みを一人で抱え込まず、専門機関に相談することが大切です。
- ケアマネジャーへの相談
介護保険サービスを利用するためのケアプランを作成してくれます。本人や家族の状況に合わせた専門的なアドバイスがもらえます
- 地域包括支援センター
認知症に関する相談全般、介護サービスの利用支援、地域のネットワークへの登録相談などに応じてくれます。
- 家族信託の専門家
将来の資産管理や契約に関する本人の意思能力が不十分になった場合に備え、財産を家族に託す「家族信託」について相談できます。
- 全国認知症家族の会
同じ境遇にある家族同士の交流会や電話相談を通じて、精神的な支えを得ることができます。
- 成年後見制度相談窓口
成年後見制度に関する法的相談や手続きの案内を受けられます。
このように、専門的な支援や地域のネットワークを活用することで、介護の負担を軽減し、本人にとっても家族にとっても安心できる環境を整えることができます。
最後に
この記事では、万一に備えるための具体的な方法をお伝えしました。認知症の家族がもし外に出て行方がわからなくなっても、事前の準備と冷静な初動があれば、早期発見につながる可能性は高まります。そして何より、介護の悩みや不安を一人で抱え込まず、外部の力を借りることが大切です。この情報が、少しでもあなたの支えとなれば幸いです。