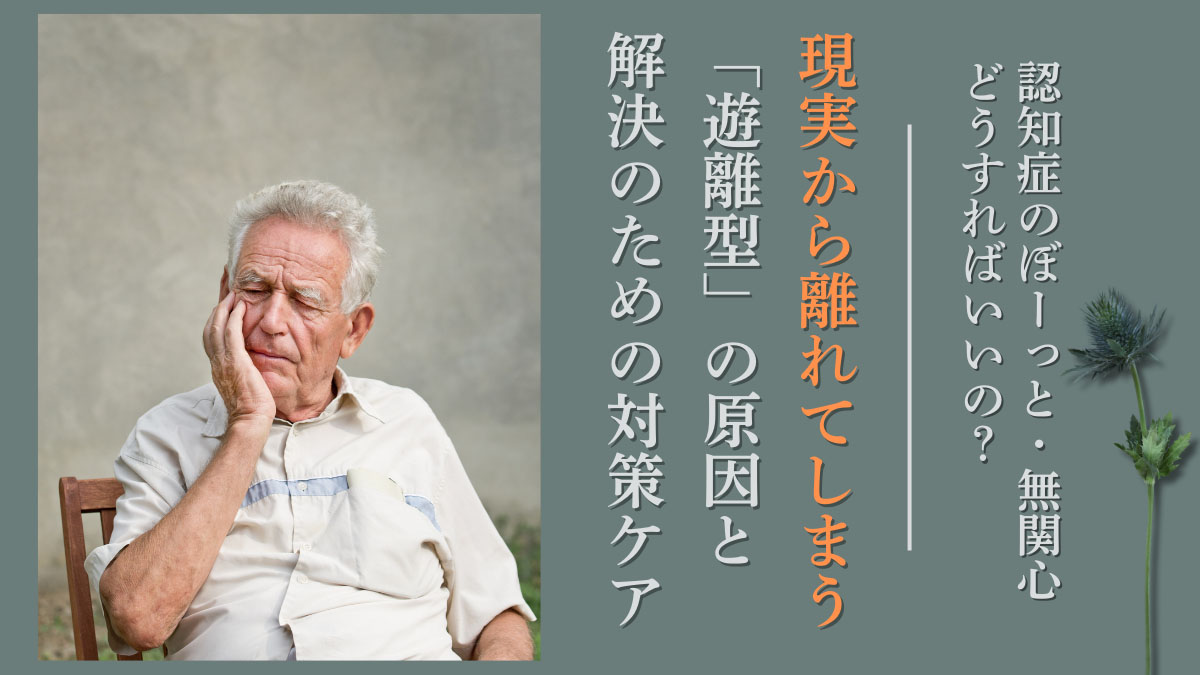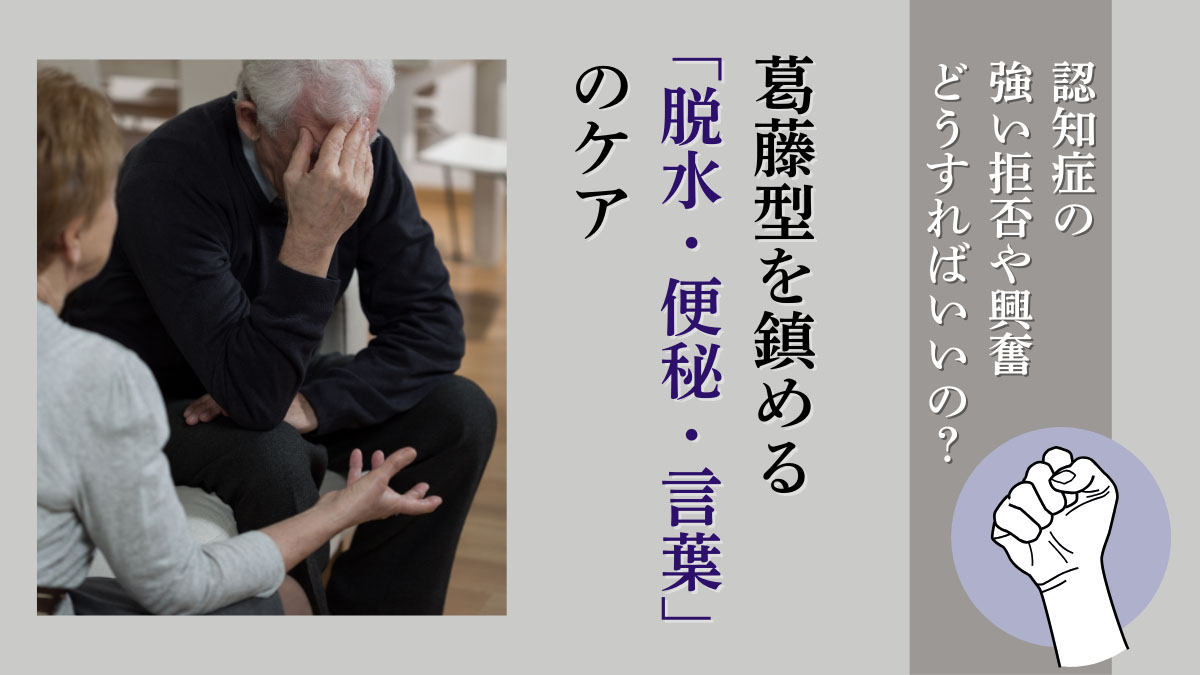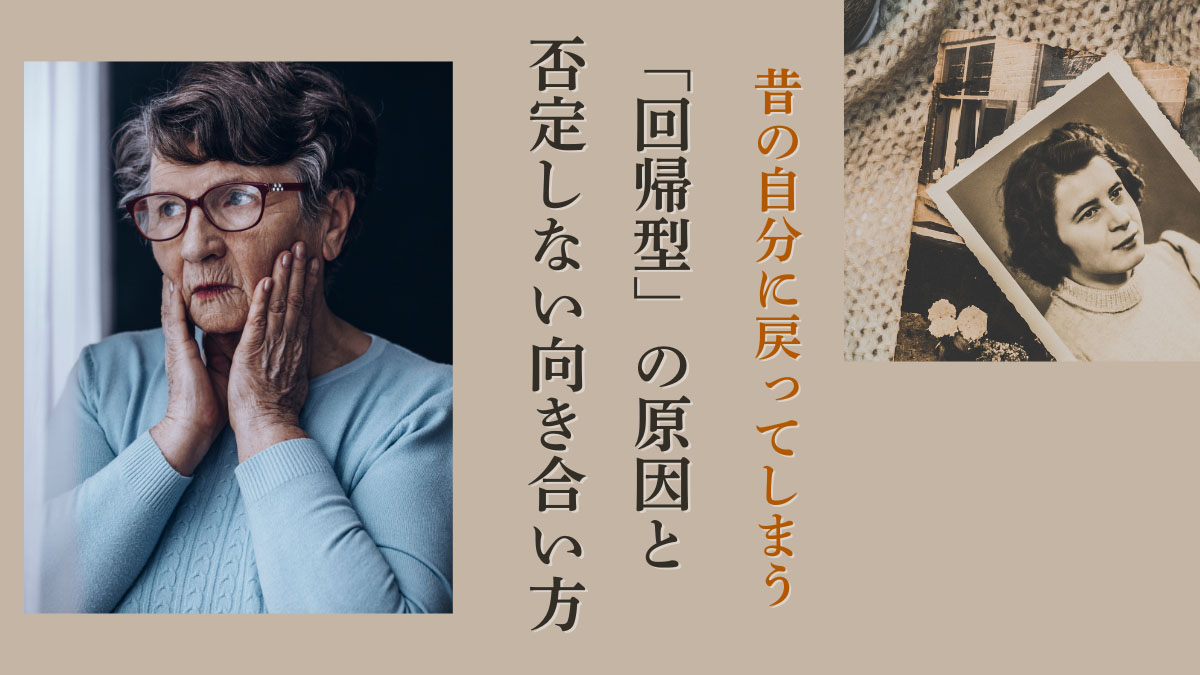
認知症の症状は人によってさまざまですが、なかには「仕事に行かなきゃ」と急に準備を始めたり、かつての職業や役割になりきって話をしたりと、まるで昔に戻ったかのような言動をする方がいます。
家族からすれば、目の前の現実と食い違う様子に戸惑いを感じるかもしれません。こうした言動は、専門用語で「回帰型」と呼ばれる状態の一つです。
この症状は、すべての認知症の方に現れるわけではありません。しかし、もし今こうした言動に直面しているのなら、そこには本人なりの「切実な理由」が隠されています。
今回は、なぜ過去に戻ってしまうのかという原因と、ご家族の負担を減らすための具体的な向き合い方について解説します。
1. 認知症の周辺症状「回帰型」とは
認知症の症状は、現れ方によって大きく3つのタイプに分類されます。
- 葛藤型: 興奮、暴言、暴力、徘徊など、周囲に対して強く反応する状態。
- 遊離型: 無気力、無関心、ぼーっとしている状態。
- 回帰型: 過去の「自分が最も輝いていた時代」や「安心できる場所」に意識が戻る状態。
回帰型は一見、つじつまの合わない「妄想」のように見えますが、本質的には「現実世界での混乱や不安から逃れ、自分が自分らしくいられた安全な場所へ避難している状態」と言えます。
なぜ「輝いていた時代」に戻るのか?
人は誰しも、今が苦しいときには楽しかった記憶に救いを求めます。回帰型が現れる背景には、本人が無意識に求めている「役割」や「安心」があります。
これらは単なる物忘れではなく、本人にとってその時代が「最も社会に必要とされ、自信に満ち溢れていた瞬間」だからこそ起こる現象です。
2. 回帰型への対処法:否定せず「過去へ一緒に戻る」

家族として最も大切な姿勢は、現実を突きつけて正そうとしないことです。「もう仕事は退職したでしょ」「今は夜中ですよ」という正論は、本人にとっては「自分の居場所を否定された」という深い絶望感に繋がります。
具体的な向き合い方の例
本人が過去の世界にいるとき、周囲はどのように接すればよいのでしょうか。先ほど挙げた事例をもとに、具体的な対応の例を紹介します。
- その時の「感情」を認める(元女優の女性)
「撮影の依頼が来た」と着替えを始めたら、「素敵な衣装ですね」「さすが、準備が早いですね」と、まずは意欲を認めます。その上で「撮影は午後からのようです。まずは温かいお茶でも飲んで、出番を待ちませんか?」と、安心できる次の行動へ誘います。
- 「役割」を尊重して共感する(元教師の男性)
「学校へ行く」と言い張る時は、「今日は日曜日だから、学校はお休みですよ」と、本人の世界観(=教師である自分)を壊さずに納得を促します。
- 同じ目線で「同行」する(元教師の男性)
どうしても納得がいかない様子であれば、否定せずに一緒に外へ出て、家の周りを一周します。少し歩くことで気が紛れ、「今日はもう遅いから帰りましょう」という言葉を受け入れやすくなることがあります。
誰かが自分の記憶や行動を認め、付き合ってくれることで、本人は「ここは安全だ」という安心感を得ます。十分に寄り添われた経験が積み重なると、不安が解消され、過去に戻る症状は徐々に落ち着いていく傾向があります。
3. 生活歴(自分史)から「安心の鍵」を探す
回帰型を理解するには、その人の「生活歴(生い立ち、仕事、趣味、性格)」を知ることが不可欠です。
過去を知ることで、一見理解不能な行動も「もし自分がこの人だったら、同じことをするかもしれない」と論理的に理解できるようになります。
家族介護者の方へ
家族だからこそ、客観的になるのが難しい時もあります。「否定してはいけない」と分かっていても、何度も同じことを言われれば、つい声を荒らげてしまうこともあるでしょう。それはあなたが本気で向き合っている証拠です。もし感情が抑えられなくなったら、その場を数分だけ離れて深呼吸をしてください。完璧な介護ではなく、あなたの心が折れないことを最優先にしましょう。
4. 体の不調が「回帰」を悪化させる? 4つの基本ケア

心のケアと同時に、身体的なアプローチも重要です。回帰型の方は一見元気そうに見えますが、脱水や便秘といった身体的な不快感があると、不安が増大し、より深く過去へ閉じこもる(または葛藤型へ移行する)ことがあります。
以下の「4つの基本ケア」を習慣化することで、精神的な安定を図りましょう。
- 水分摂取:1日1,500mlを目安に。脳の血流を維持し、意識をハッキリさせます。
- 食事:1日1,500kcal程度。栄養不足は脳の混乱を招きます。
- 排便管理:便秘による不快感は、周辺症状を顕著に悪化させます。
- 適度な運動:1日2km程度のウォーキングまたは30分程度の運動など。適度な疲労感は質の高い睡眠に繋がり、日中の混乱を抑えます。
最後に:現実も「悪くない」と思ってもらうために
回帰型は、その方が人生の中で「一生懸命に輝いていた証拠」でもあります。
無理に今へ引き戻すのではなく、過去の記憶に一度一緒に降り立ってみてください。本人が「この人は分かってくれる」と安心できたとき、現実の世界も「そう悪くない場所だ」と感じてもらえるようになります。
まずは1杯の水分補給と、本人の「かつての活躍」に耳を傾けることから始めてみませんか。