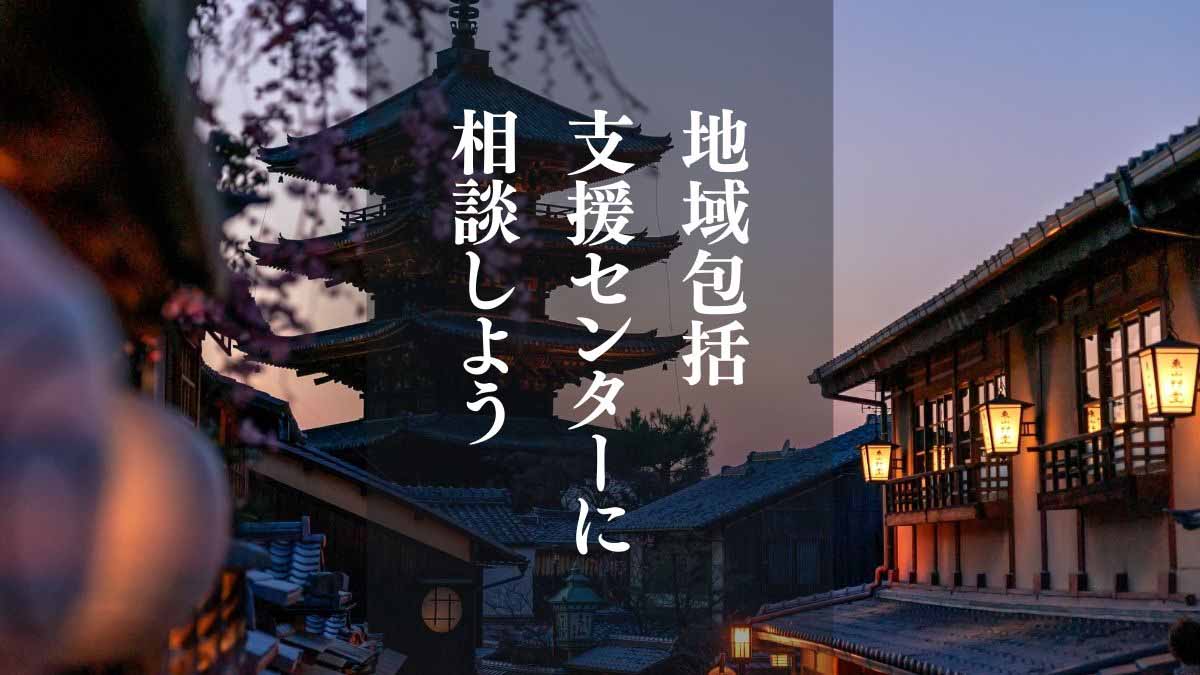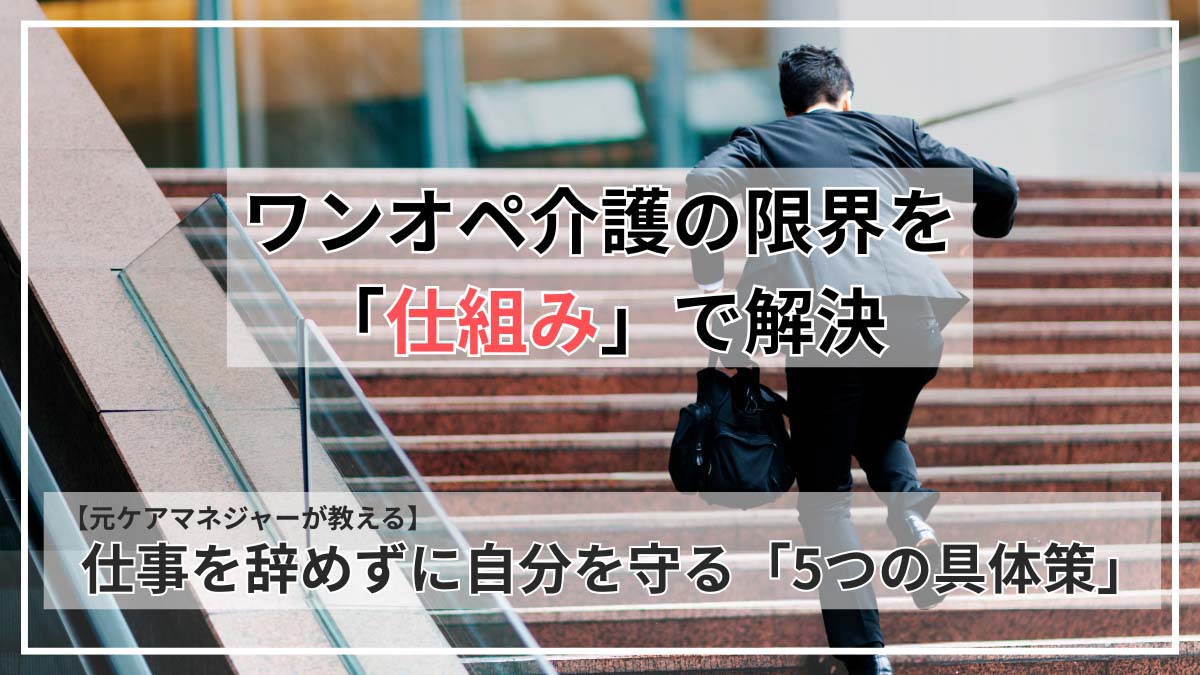
「今日も寝不足のまま出勤しなければならない」
「職場で急な呼び出しがあったらどうしよう」
一人で介護を担う当事者にとって、仕事との両立は綱渡りのような毎日です。責任感の強い人ほど「自分が頑張ればいい」と抱え込みやすく、結果として生活の土台が崩れてしまうリスクがあります。
本記事では、これから介護が始まる方や、始まったばかりで何から手をつければいいか不安を感じている方へ向けて、元ケアマネジャーの視点から生活とキャリアを守り抜くための「具体的な手順」と「心の持ち方」を解説します。
この記事の結論
なぜ「ワンオペ介護」はあなたを追い詰めるのか

在宅介護における「ワンオペ」が、仕事や育児のそれよりも過酷だと言われる理由は、その「逃げ場のなさ」と「無期限の拘束」にあります。
一般の仕事や家事には、一日の終わりを告げる「閉店」があります。しかし、在宅介護、特に一人で担う状況下では、責任のすべてが24時間365日休みなくあなたにのしかかります。
増え続けるワンオペ介護の現実
こうした深刻な事態が起きるのは、個人の問題ではありません。少子高齢化や未婚率の上昇、さらには兄弟姉妹が遠方にいるといった「家庭環境の変化」により、負担が一人に集中せざるを得ない構造が社会全体で広がっているからです。
「自分がなんとかしなければ」という責任感は大切ですが、まずは今の状況が個人の努力だけでは支えきれない限界にあると正しく認識することが出発点です。
身体と心を「消耗」させる負担
ワンオペ介護では、家事と介護のすべてを一人で担うため、心身への負荷が休む間もなく蓄積していきます。
- 身体的な影響
トイレ介助や移乗などの力仕事、さらに夜間対応による慢性的な睡眠不足がエネルギーを奪います。
- 精神的な影響
心身の消耗は、感情のコントロールを失わせる「介護うつ」などの危険性があります。これは個人の資質の問題ではなく、一人ですべてを担うこと自体に無理があるのです。
キャリアを断絶させる「介護離職」のリスク
夜中の対応で睡眠が削られれば、仕事のパフォーマンス低下は避けられません。こうした心身の限界や、仕事との両立が困難な環境に追い込まれ、結果として「介護離職」を選択する人は年間約10万人にのぼります。しかし、離職は経済的な不安を招き、介護生活をさらに厳しくする悪循環を生んでしまいます。
仕事とワンオペ介護を両立させる「5つの仕組み」

今の生活を維持し、共倒れを防ぐためには、以下の5つのポイントを意識してみてください。
ポイント1:まずは介護相談の入り口「地域包括支援センター」へ
介護の負担を一人で抱えないための第一歩は、お住まいの地域の「地域包括支援センター」に相談することです。ここは、介護保険の申請やサービスの調整をトータルで支えてくれる介護相談の総合窓口です。
窓口で「ワンオペ状態で限界が近い」ことを正直に伝え、要介護認定などの手続きを進めることで、のちに実務を担うケアマネジャーへとスムーズにバトンを繋ぐことができます。
ポイント2:介護保険サービスを「最大限」に活用する
仕事と両立するためには、自分で行う介護を最小限にし、プロの力を借りる「割り切り」が必要です。
【在宅介護で活用できるサービス例】
- 訪問介護(ホームヘルプ)
仕事での不在時や忙しい時間帯の介助を依頼します。ただし、同居家族がいる場合は、同居者の役割とされる一般的な家事(掃除・洗濯・調理など)にはサービスが適用されないルールがある点に注意し、ケアマネジャーと相談して支援範囲を定めましょう。
- 通所介護(デイサービス)
日帰りの施設に通うことで、日中の安全・安心を得ることができます。仕事が土日休みの場合は、あえて土日営業の施設を選び、自身の休息や家事に充てる「自分のための時間」を確保することも大切です。
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
数日から1週間程度、施設へ入居するサービスです。仕事の繁忙期や自身の体調不良時はもちろん、介護者の心身をリフレッシュさせる「計画的な休息(レスパイト)」を目的とした活用も、共倒れを防ぐためには欠かせない選択肢の一つです。

ポイント3:介護休業制度を「介護に専念するため」に使わない
介護休業などの制度は「育児・介護休業法」によって定められており、たとえ勤務先の就業規則に明記されていなくても、全ての労働者の「権利」として認められています。
具体的には、「介護を理由とした休業の取得」を会社は拒否できず、それを理由に解雇や降格といった不利益な扱いをすることも法律で禁じられています。
ただし、使い道には注意が必要です。介護休業は「自分が介護に専念するための休み」ではなく、「仕事と介護を両立できる体制(仕組み)を整えるための休み」と考えてください。休業期間中にケアマネジャーと連携してプロの手を借りる体制を構築し、スムーズに復職できる環境を作ることが本来の目的です。
ポイント4:介護のプロには「頼る・任せる・依存する」でいい
「親の介護は家族がすべて担うべき」という考えは、現代の社会構造では非常に困難です。 自分一人で解決しようとせず、プロの力を借りて「健全に依存する」という考え方を持ってください。
ここで言う「健全に依存する」とは、「手」が必要なことはプロに任せ、自分は「心」のケアに集中することです。
- プロの役割(手)
食事や入浴、排泄の介助、日中の見守りなど、体力と技術を要する実務
- あなたの役割(心)
親との会話、体調の変化への気づき、そして「これからの生活」を一緒に決めること
すべてを抱え込むと、余裕がなくなって親に優しく接することができなくなります。実務をプロに任せることで、あなたは「介護者」という役割から、本来の「息子・娘」という立場に戻ることができます。
ポイント5:自分自身の生活を「最優先」に設計する
介護を生活の中心に置くのではなく、まず「自分の生活と仕事」という基盤があり、その上に介護を組み込むという視点を持ってください。
- 「万が一」に備えた選択肢の確保
将来的に在宅継続が難しくなる可能性に備え、施設情報などを早めにケアマネから得ておきましょう。これは親を「見放す」ことではありません。いざという時の逃げ道を持つことが、今の生活を続ける「心のゆとり」になります。
- テクノロジーの導入
見守りカメラやスマートフォンのGPS、ICTを活用した関係者連絡ツールなどを積極的に取り入れましょう。不在時の不安を減らすことが、仕事への集中力を維持し、生活の質を保つ助けとなります。
最後に:一人で背負わず、チームで「暮らし」を守る
ワンオペ介護と仕事の両立は、精神論ではなく「仕組み」で解決すべき課題です。
「介護はの実務はプロに任せ、自分は家族としての心と自分の人生を大切にする」
この姿勢こそが、結果として親との良好な関係を保ち、あなたのキャリアを守る近道になります。一人で悩む時間を、プロに相談する時間に変えていきましょう。